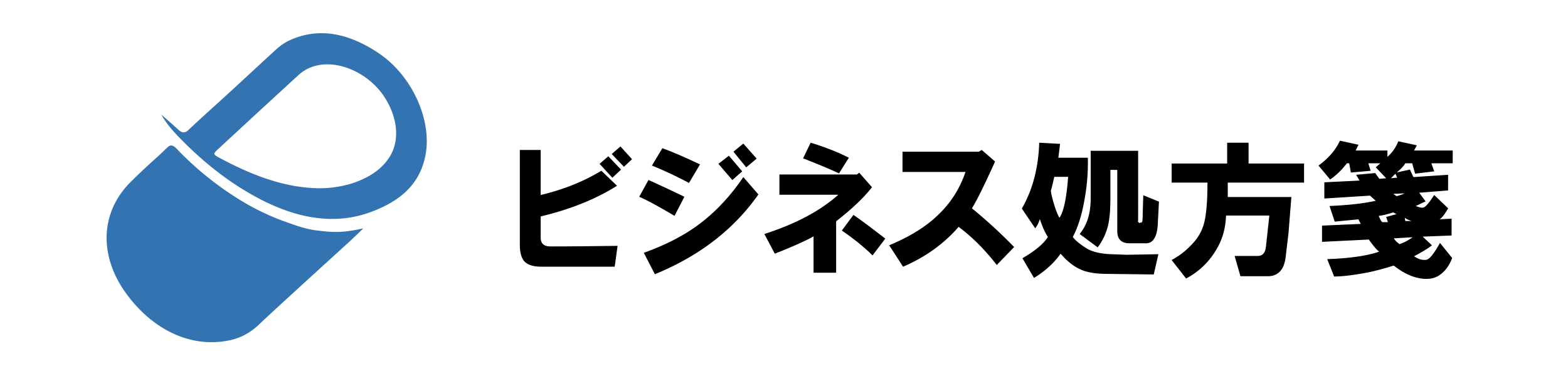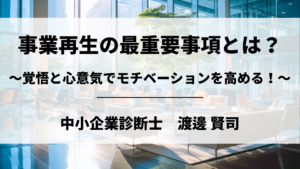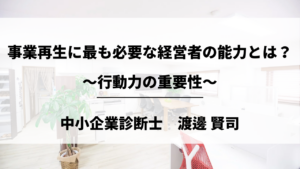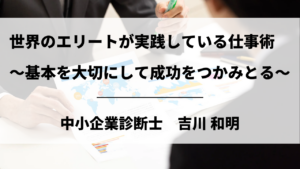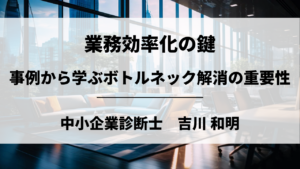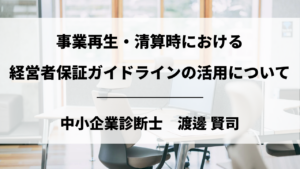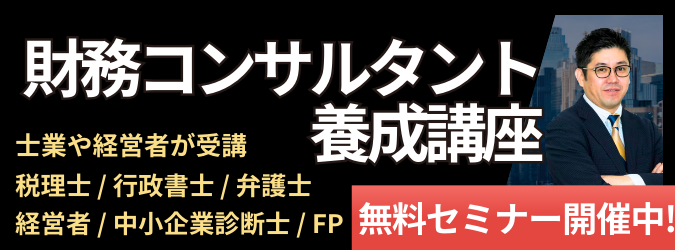会社のパワーハラスメント(パワハラ)の対応と判例

前田 竜徳
人事コンサルタント
株式会社ヒューシーク 代表取締役 / 日本大学 非常勤講師
大学卒業後、ノンバンク(東証1部上場)に就職し、本店営業部配属。その後、マネジメント経験を積むためベンチャー企業へ転身。本部スタッフ、店舗統括マネージャー、経営企画室長を歴任。新規採用、法人営業、銀行や投資家との資金交渉、株主総会の準備・運営、助成金・補助金の申請など幅広い業務を担当。
2007年 独立し、中小・零細企業を中心に「マネジメント」や「人材育成・採用」の支援を行う。2009年、株式会社ヒューシークを創業し、代表取締役に就任。
ハラスメントとはどういう状況か
まずはハラスメントとの現状を知るため、ハラスメントとはどういう状況かについて説明します。「ハラスメント」と聞くと「パワハラ」や「セクハラ」という言葉が最初に頭に浮かぶかと思います。
厚生労働省の調査によると、「過去3年間パワハラを受けたことがありますか?」という質問に「ある」と回答した人は全体の32.5%でした。個人的には意外に多いように感じます。
ハラスメントを受けたことが「ある」と答えた方に対しての「ハラスメントを受けた後どうしましたか?」という質問には「何もしなかった」が一番多く、40.9%でした。結構な割合の方がパワハラを受けながらも、その後何も対応することなく我慢をした、もしくは何もせず会社を退職していったということになります。つまり、今世間でパワハラとしてニュースに挙がっているものは氷山の一角であり、我々が知らないところで相当数パワハラが行われ、そのままになっているということです。
別の厚生労働省の調査結果では、労働局監督署の相談窓口に増加している相談内容が「いじめ・嫌がらせ」です。。
「相談内容と相談者の雇用形態」の調査でも「いじめ・嫌がらせ」が多いという結果が出ています。そして雇用形態としては正社員が一番多いです。
ハラスメントは法律で定義づけされている
次にハラスメントとはどんなことかを確認していきます。下記3つを全て満たすものを「ハラスメント」と定義付けられています。
- 優越的な関係を背景とした言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
- 労働者の就業環境が害されること
「優越的な関係」というのは上司部下の関係がわかりやすいです。上司が自分の仕事上での権限を超えて、部下の就業環境を害することをハラスメントといいます。そのハラスメントが暴力的なものになるとパワーハラスメントになります。性的なものであればセクシャルハラスメントになるのかなという風にご理解ください。
また、数多くあるハラスメントの中で、国は現在「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」に注力しています。これは対応として足らないところもあるように個人的には感じています。
職場におけるハラスメントとは
ハラスメントに気を付けて行動するあまり、経営者や上司として、しかるべき対応ができなくなってしまうこともあります。
「これはハラスメントに当たりますか」といったご相談をよくいただきます。解答は「業務上の適正な範囲であればハラスメントにはなりません」です。叱責であろうと厳しい指導であろうと、業務上の適正な範囲を超えていなければハラスメントには当たりません。
例えば、取引先のアポイント時間を間違えて、部下が遅刻した時に同行した上司が「何をやってるんだ」と注意した。これだけではハラスメントにならないのです。ただし、この「何をやっているんだ」に追加して「だからお前とは仕事をしたくないんだ」「噂通り役立たずだなぁ」「仕事しなくていいから帰って寝てろ」などを言ってしまうと人格否定となり、業務上の適正な範囲を超えたとみなされてハラスメントとなります。ですので、「業務上の適正な範囲を超えない」で部下の成長を促していくというのがポイントになります。経営者・会社上司の方がハラスメントに注意しすぎずにしっかりと会社運営をしていただければと思います。
ハラスメントの何が問題なのか
ハラスメントが起こす問題について考えていきます。ハラスメントがあった職場ではどういった負の結果が出てしまうのでしょうか。
社員の影響としては、心身の健康を害し休職等に至ってしまう、職場環境が悪化してしまう。会社への影響は、モラルの低下から会社全体の生産性が下がり業績が悪化してしまう、より良い人材が流出してしまう、訴訟による賠償によりコストがかかるため業績が悪化してしまう、企業のイメージの悪化で採用活動・営業活動への影響が出てくることが挙げられます。
その他、コンプライアンス上の問題になります。ハラスメントは民法、刑法、就業規則違反に該当しますので、しっかり遵守していく必要があります。
厚生労働省のアンケート結果では「職場の雰囲気が悪くなる」「従業員の心の健康を害する」「従業員が十分に能力を発揮できなくなる」といった形でハラスメントをした人や受けた人だけではなく、会社全体に悪い影響をもたらすことも理解ください。
「パワーハラスメント等の防止対策の強化」について
令和4年4月1日に施行された中小企業のハラスメントと関係のある法制について、ポイントをご紹介していきます。
①事業主及び労働者の責務の明確化
職場におけるパワハラの内容、パワハラを行ってはいけない旨の方針を明確にし、労働者に周知・啓発を行わなければなりません。つまり、令和4年4月1日以降、零細企業や個人事業主を含めた中小企業は、会社の中で「パワハラを行っていけない」という方針を文章化して、労働者に周知・啓発をしなければいけないとういことです。これは、社内掲示板への掲示、社内のイントラネットへの搭載、各従業員にメールで配布、就業規則に定めるなどの方法が考えられます。
②相談窓口を設置の義務化
パワハラを受けたときやパワハラを見たときはここに相談する、という窓口を社内に設ける必要があります。社内で設けることができない場合は、外部機関と連携してこの外部機関に相談窓口を設けてくださいという内容です。これは結構手間がかかりますが、法律上義務化されているので対応しなければいけません。
その他、③④と続きますが、①②の派生条項なのでここでは割愛します。
まずハラスメントについての方針を明文化して、方針発表しすること、相談窓口を設置すること。この2点の対応が必要です。
なぜハラスメントが起きるのか
次は視点を変えて、なぜハラスメントが起きてしまうかについて、7つ列挙します。
- 「しごく」ことで人が動くという誤解
これは昭和的な営業スタイルと見受けられそうですが、失責をすることによって人は頑張るのではないかというような誤解がいまだに持っている人がいます。 - 感情のヒートアップ
上司が感情的になってしまって、感情を部下の方にぶつけてしまうというような時にハラスメントが起きてしまうことです。 - 残業が多い・休みが取りにくい
心身ともに余裕がなくなった時に人に当たってしまうというような場面が想定されます。 - 失敗が許されない、失敗への許容度が低い職場
組織風土として捉えられると思います。 - 競争の激化、業務が多忙、業績不振などの職場環境の変化
- 雇用形態の多様化、意識の変化
年代や雇用形態が複雑になり、ある一定の年齢の方が若い方への感情がなかなか理解できない、どう接していいのかわからないということでパワハラが起きてしまう場合もあります。 - 古い職場の体質や企業風土、倫理観の欠如
ハラスメントを予防するにはどうしたらいいか
- ハラスメントについての十分な理解・関心を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
- ハラスメントにならないためのコミュニケーションを心掛けること
- 円滑な職場コミュニケーションの醸成・業務上の指示や指導・教育の適切な方法の理解すること
叱る対象や理由を明確にすること、自分の感情を認識して、相手を攻撃せず適切な指導をしていくことが重要です。相手の性格や、その時に相手が置かれた環境を理解してあげた上で指導をしていきましょう。 - 隠れたハラスメントがないか、周囲のメンバーの変化に注意すること
- ハラスメントを起こさせない職場環境づくりを管理職が理解すること
- 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力をすること
ハラスメントはパワハラ・セクハラ・マタハラだけではない
ハラスメントは、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントだけではありません。〇〇ハラと呼ばれるものをいくつか紹介します。
仕事に関するハラスメントから、ライフステージに関するもの、性別、国性、宗教に関するものがあります。
カスハラ
「カスタマーハラスメント」の略です。最近よく話題になり、カスタマーセンターへの暴力的な言葉のハラスメントなどがあります。主に電話越しが多いです。
オワハラ
「就職活動終われハラスメント」の略です。内定を出した会社が、就活生に他の会社は受けず、選考は断ってうちの会社に来なさいと、就職活動を終わらせるよう誘導することです。
ゼクハラ
「ゼクシィハラスメント」の略です。「何で結婚しないのか」といったライフステージに関する内容を発言することです。
スメハラ
「スメルハラスメント」の略です。臭いにより周囲の人に悪影響を与える行為を指します。具体的には、体臭や口臭だけでなく、香水のつけすぎや過度な柔軟剤の香りなど、香りをまとっている本人がよいと思っていても、周りが不快に感じる場合に該当します。
セカハラ
「セカンドハラスメント」の略です。「セカンドハラスメント」とは、ハラスメントを受けた人がその被害を周囲に相談した際に、逆に嫌がらせを受けたり、相談者自身が責められたりするなど、ハラスメントの二次的な被害を指します。
ハラハラ
「ハラスメントハラスメント」の略です。自身が感じる不快な思いに対して過剰に「ハラスメントだ」と主張する行為のことです。具体的には、部下が上司に対して「なんかやだな」と感じた際に「パワハラですよ」と脅すような行為がハラスメントハラスメント(ハラハラ)に該当します。また、休日に関することをたずねたり、子供の体調不良で急に休んだ従業員に対して「子供の様子はどう?」とたずねただけでハラスメントを主張するケースもあります。
このように様々な種類のハラスメントがあります。
実際にハラスメントが起きてしまったら
実際ハラスメントが起きてしまった時、どういう流れを取ればいいのでしょうか。
まずは法整備されている社内相談窓口、もしくは外部委託先に本人(相談者)との面談を行います。
それから事実関係の確認です。実際にハラスメントをした行為者や、その周りの第三者からのヒアリングを行います。これは必ず相談者の了解のもと、行います。
そして、各人への対応を検討し、対応措置を行います。場合によっては行為者に対して、けん責、減給、降格、出勤停止、懲戒解雇等の処分を行います。
そして相談者と行為者へのフォロー、再発防止という流れです。
再発防止は法律で義務化されています。一度起きたことは二度と起きないように、管理職員の研修を行う、全従業員向けのハラスメントの研修を行うなどして、再発防止を務める必要があります。
ハラスメントに関する判例
ハラスメントに関する判例は多くあります。こちらで2つご紹介します。
「A病院に勤務していた看護師Bは、先輩看護師のCから飲み会の参加共用や個人的用務の使い走り、暴言等のいじめを受け、自殺した。」
こういった、ハラスメントを受けた方が自殺したという厳しい内容の判例があります。
「鉄道会社Dに勤務するEは、鉄道組合のマークが入ったベルトを身につけて作業に従事していたところ、上司Fが就業規則違反を理由に取り外しを命じ、就業規則全文の書き写し等を命じ、手を休めると怒鳴り、用便に行くことを容易に認めず、湯茶を飲むことも許さず、腹痛により病院に行くことも聞き入れなかった」
これはどう見てもやりすぎであることがわかるかと思います。
このように、色々な判例がありますので、是非機会があれば確認してみてください。
今回はハラスメントについてご紹介していきました。
社内でハラスメント研修を実施して、社員同士でハラスメントに関する共通認識を持っておくことも効果的です。
講師に無料相談をする
ビジネス処方箋に登壇している講師に無料相談を行うことができます。
お問い合わせいただきましたら、ご相談内容に適した士業・経営者の講師をご紹介いたします。