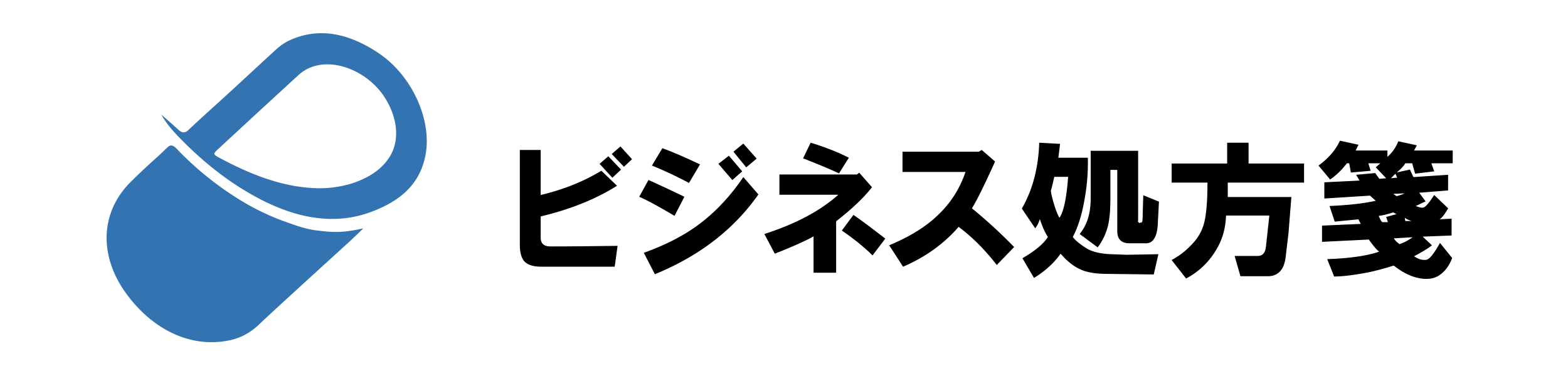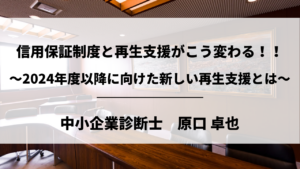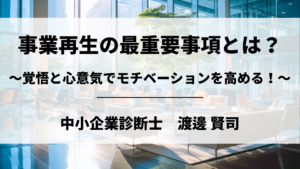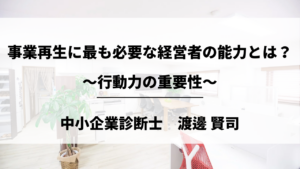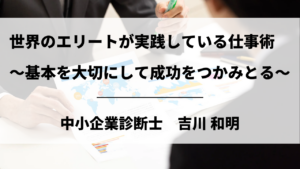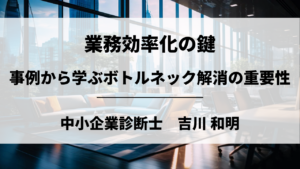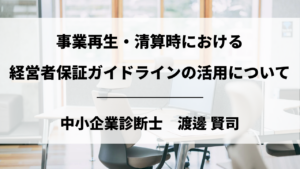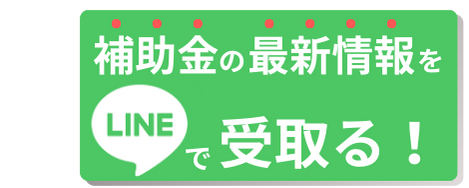【節税対策】中小企業の社長が最低限抑えておくべき消費税の仕組とインボイス制度の知識| Part2
登壇者

園田 洋司
税理士
園田会計事務所
都内の税理士法人等で、中小企業から、上場企業、医療法人、公益法人等の税務支援などに従事。2008年に開業し、中小企業の税務支援ほか、オーナー企業の経営者に対する事業承継支援、相続対策などを行う。
キャッシュフローコーチ®、銀座コーチングスクール認定のコーチとしても活動し、経営者と対話を通じて、経営者の自発的な行動支援など行う。
本シリーズは二部制で、上記の動画は「Part.2」です。
▼ シリーズ動画一覧
目次
講師に無料相談をする
ビジネス処方箋に登壇している講師に無料相談を行うことができます。
お問い合わせいただきましたら、ご相談内容に適した士業・経営者の講師をご紹介いたします。