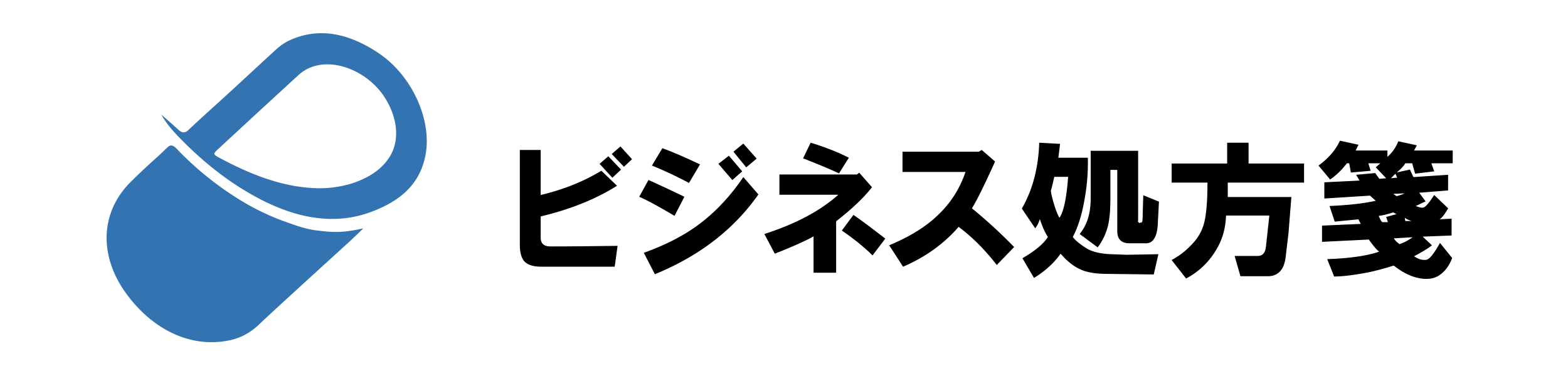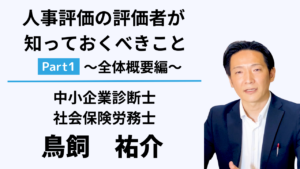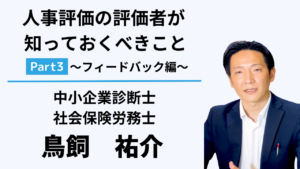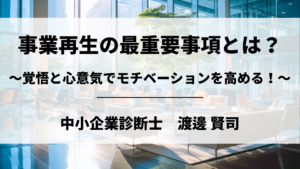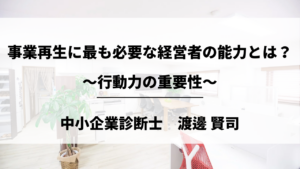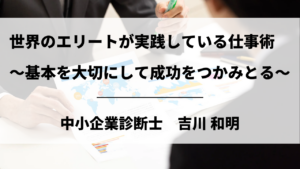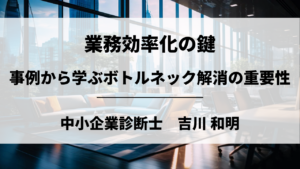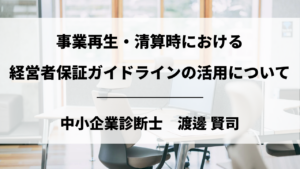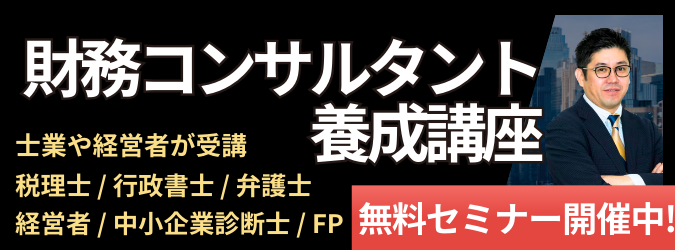人事評価の評価者が知っておくべきこと| Part3 フィードバック編

鳥飼 祐介
中小企業診断士/
社会保険労務士
経営人事総合事務所クリエイションハイブ
大学卒業後、事業会社の人事部業務全般に従事し、総合コンサルファームに転職後は人事労務を専門にコンサルティング業務を行う。
主に、株式上場(IPO)を目指す企業の労務管理体制構築や、人事制度構築の支援実績を積む。2021年8月独立後、専門性の高いノウハウを活かし、プライム上場企業から中小零細企業まで顧問活動を行う。企業の人材確保が難しい中、現場に入り込んだハンズオン(半常駐)型の改善支援を積極的に展開している。
本シリーズは三部制で、上記の動画は「Part.3」です。
▼ シリーズ動画一覧
はじめに
「人事評価の評価者が知っておくべきこと」と題して、最終回はフィードバック編について解説します。
フィードバックの目的・手順・内容
フィードバックの位置づけとしては、人事評価プロセスの最終的な段階になります。最終的な評価が決定した後に、フィードバック面談を通じて被評価者(部下)に直接その評価結果を伝えます。
このフィードバックを行うにあたっての目的や手順、内容について説明します。
①目的
フィードバックの目的には大きく分けて2つあります。
1つが今期の業績や結果に対する認識のすり合わせを行うこと、もう1つが今後の成長目標とその施策のすり合わせを行うことです。
②手順・内容
フィードバックを行う際の手順や内容について説明します。
まずは、今期を振り返り、今後改善すべき課題の明確化とすり合わせを行うことがフィードバックの目的であることを被評価者(部下)に伝えます。自分の評価が良くなかったから叱られるとか、給料が下がってしまうといった、後ろ向きな面談ととらえられないように注意が必要です。
次に、被評価者(部下)本人から今期の自己評価について説明してもらいます。どのように自分自身を評価しているのか、自己評価の根拠となった具体的な業績・行動上の事実は何かを説明してもらうのです。
評価者は、自己評価内容や本人の説明の中に不明な点がないか、あるいは評価者・被評価者(部下)間で認識の異なる評価事実はないかを十分に確認します。
最後に、今後取り組むべき目標と施策、改善点を示した上で、評価者・被評価者(部下)間で具体的なすり合わせを行います。そして評価者として、被評価者(部下)が成長するための支援や配慮すべき項目があれば、面談の中でしっかりと伝えることが重要になります。
フィードバックのポイント
被評価者(部下)の育成やモチベーション向上が目的であることを十分に意識して、評価者自身の言葉で伝えることが重要なポイントになります。
評価結果の説明を行う場合の基本的なパターンは3つあります。
①評価結果が標準を上回る場合
これは、フィードバックが非常にやりやすいケースになります。基本的には褒めて、良かった点や高評価の理由を添えて説明し、今後も継続して頑張るように期待を伝えることがポイントになります。
さらに、より高いチャレンジ目標や、より高い行動への期待と課題を合わせて伝えることが重要になります。
②評価結果が標準的な場合
これは、良かった点や反省すべき点、今後努力すべき点を説明するケースになります。ここで注意すべきことは説明する順番です。フィードバックの最後に反省すべき点というマイナス面の話で終わってしまうと、被評価者(部下)がフィードバック面談をネガティブにとらえてしまう傾向にあるためです。
説明する順番としては、先にネガティブ要素を出した後に、ポジティブ要素で締めくくるというのが1つのポイントになります。
③評価結果が標準を下回る場合
これは、非常にフィードバックがしづらいケースになります。今回の評価での反省と今後の課題を、具体的かつ明確にすることが重要です。
評価が低かった部分を簡潔に伝えた上で、今後の頑張りや具体的な課題を中心に話を進めます。最後に、「必ずできるはずだと」いう前向きな期待を忘れずに伝えることがポイントになります。
④評価内容についての丁寧な説明
評価者全員が完全に同じ目線で評価することが実際不可能なため、100 %公平な評価制度というのは難しいです。だからこそ、評価者が評価内容について丁寧に説明することが重要になります。また、評価者は被評価者(部下)が納得する情報や機会を提供することも重要であり、事前に準備をしておく必要があります。
日頃の言動を観察すること、これはフィードバックに限らず、人事評価制度をうまく運用するにあたって非常に重要な考え方になります。被評価者(部下)の言動を日頃から観察することによって、被評価者(部下)の成長を確認することもできますし、逆に課題点を把握することもできます。
また、コミュニケーションを怠らないことも非常に大切です。被評価者(部下)と常日頃からコミュニケーションをとることにより、評価結果の認識の齟齬を回避することもできます。
さらに、丁寧な説明をして、本人の成長のための十分なバックアップ体制を作ること、そして評価者としての真摯な態度をとることも、評価の納得性を高めるポイントになります。
フィードバックは評価結果を伝えるだけでなく、被評価者(部下)本人の成長意欲を向上させるために行うものです。被評価者(部下)本人には、なぜそのような評価となったのかを理解をしてもらうこと、評価者としては、被評価者(部下)本人が評価結果に対しどのように感じているのかを理解することが重要です。
疑問点があれば丁寧に説明し、今後の取り組み方針として何が必要かを具体的にアドバイスすることも忘れてはいけません。
「いつもあなたのことを見ていますよ、しっかりと評価していますよ」という気持ちを伝えて、今後の成長のための相互理解を図ることがポイントになります。
フィードバックの注意点
フィードバックを行う上での、主な注意点は以下の通りです。
①被評価者(部下)と話をしている内容が漏れないように、個室などで面談を実施すること
②評価者からの一方的な説明とならないこと
③被評価者(部下)の話は丁寧に聞くこと
④被評価者(部下)の意見に対し、すぐに押さえつけないこと
上記の内容については徹底されていないケースも見受けられますので、あらためて確認しましょう。
フィードバックの具体的な流れ
フィードバックの具体的な流れは以下の通りです。
①事前準備
評価シートを確認して、被評価者(部下)に対して評価結果をどのように伝えるのか、また、想定される反応や、被評価者(部下)からの質問への対応などを事前に準備します。
②目的を伝える
評価期間を振り返って、被評価者(部下)本人の業績や能力、取り組み姿勢を評価するものであるということを伝えます。そして評価結果は評価者自身だけでなく、会社としての人事評価結果であることを伝えることが重要です。
③リラックスをさせる
フィードバック面談をより充実した内容とするために、被評価者(部下)の緊張をほぐすよう雑談などを入れます。採用面接でもよくある「アイスブレーキング」の手法です。
④評価結果の内容を伝える
評価結果を伝える前に、評価期間中にどのような業績があったのか、能力の向上度合いや勤務態度なども含めた根拠を明確にした上で、具体的に評価結果を伝えます。
⑤質問や意見を聞く
被評価者(部下)本人の評価結果に対する感想を聞いてあげます。評価結果に対して実際にどう思っているのか、率直な意見を述べてもらうことが大切です。その中で疑問点があれば、丁寧に説明をすることが重要です。
⑥今後の方針について話し合う
改善点や期待する役割、業務を伝えて、被評価者(部下)自身の今後の仕事に対する希望や悩みについて聞いてあげます。さらには、今後に向けて「何を」、「いつまでに」、「どのようにする」のかを話し合い、お互いにイメージを共有することが大切です。
講師に無料相談をする
ビジネス処方箋に登壇している講師に無料相談を行うことができます。
お問い合わせいただきましたら、ご相談内容に適した士業・経営者の講師をご紹介いたします。