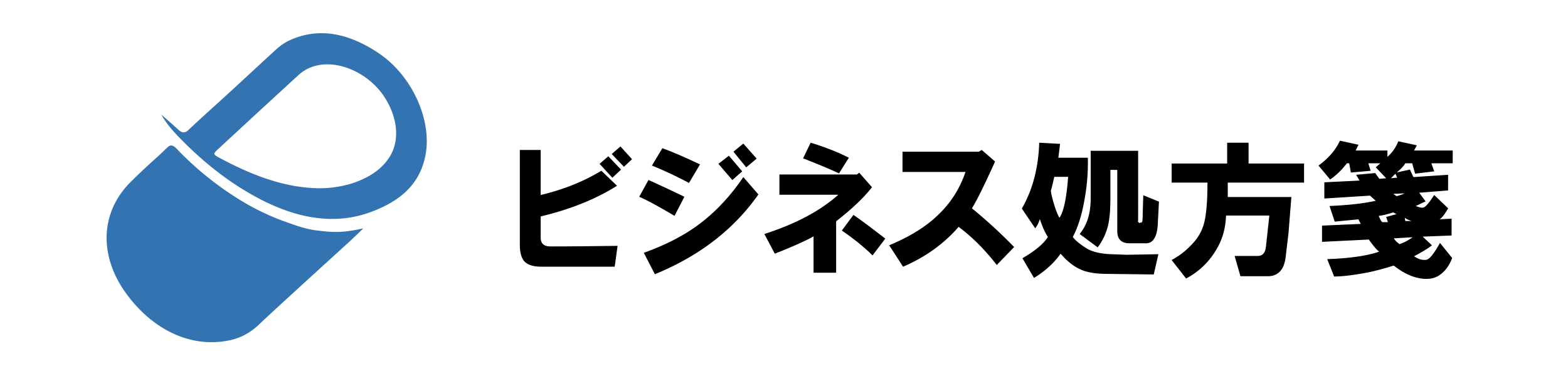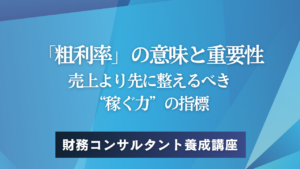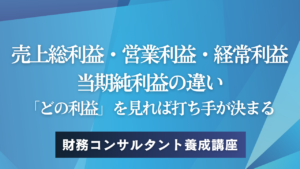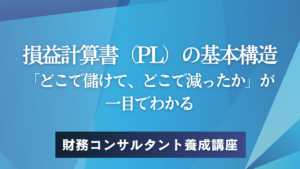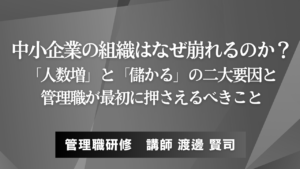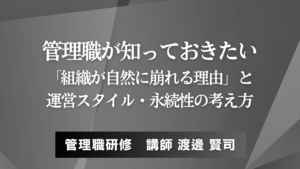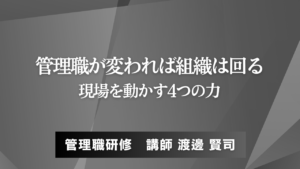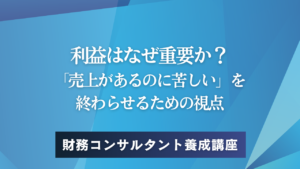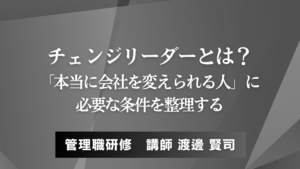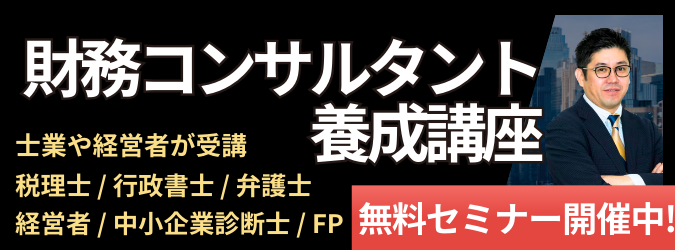収益性判定のものさし

利光 洋一
公認会計士/税理士/
中小企業診断士
合同会社TRUE CAUSE 代表 利光 洋一 / 利光公認会計士・税理士事務所
中堅監査法人で、上場・非上場企業の会計監査を中心に多数関与。
その後、税理士法人とコンサルティング会社の両社に所属し、コンサルティング会社では執行役員として複数の財務・税務デューデリジェンス等を主導。
2021年に経営計画策定や業務改善を中心とする合同会社を設立、会計・税務全般を請け負う利光公認会計士・税理士事務所を開設。利益への貢献を主軸としている。
はじめに
今日は、「収益性判定のものさし」というテーマでお話をします。
製品の収益性がどうかという議論は、ビジネスの世界では珍しくないと思います。ただ、明確な判断基準を持って収益性の良し悪しを判定しているところは意外に少ないように思います。今日は、自社独自のものさしを作って、そのものさしで製品ごとの収益性を図っていく方法をお伝えします。
利益構造モデル
収益性判定のものさしを作る上で、まずは全社的な利益構造を掴むことが重要です。
付加価値という概念を使ってものさしを作っていくわけですが、その付加価値を算出するために、費用を変動費と固定費に区分する必要があります。変動費は売上の増減に応じて増減する費用で、固定費は売上の増減に関わらず一定額発生する費用です。
私の経験上、変動費は材料費と外注費のみでほぼ有用な分析が可能です。小売業であれば商品仕入れということになります。もちろん、やってみて想定値とかけ離れるようようなことがあれば、自社特有の事情に応じて調整をかけていくことも必要ですが、そこにこだわり過ぎると複雑で使えないものになってしまうため注意が必要です。
このように利益構造を掴むことで、利益から逆算して付加価値が求められるようになります。
全社的目標となる付加価値
次に自社独自のものさしを作る手順をお伝えします。まずは理論としてお伝えして、その後に具体例で数値を使ってお伝えします。理論と数値を使った具体例の両方で理解を深めていただければと思います。
まずは理論からです。
利益構造がつめたら、目標利益から全社的目標となる付加価値を算出します。目標利益の考え方は前回の動画でもお話ししましたが、会社は獲得した利益から税金を支払い、借入金の返済を行い、現在の事業だけでは心もとないので未来事業への投資をし、その上でコロナなどの不足の事態の備えも必要になってきます。
しかし、会社によっては配当が必要な会社もあります。この点をよく考え、目標利益を決めます。そして逆算して目標付加価値を算出します。具体的には目標利益プラス固定費です。
次に、その目標利益を直接作業時間で割って、1時間あたりの目標付加価値を算出します。1時間あたりの目標付加価値の意味合いは、外部から材料を仕入れて、自社で加工して、顧客に販売される流れの中で、自社を通っていく間に、毎時間いくらの価値を加えているのか、言い換えれば、毎時間自社でいくらの価値を付加できているのかということです。
そして、1時間あたり付加価値というのは、1時間あたりに付加したいと会社で目標にしている付加価値ということです。分母となる直接作業時間については次のスライドで解説していますが、加工因数が分かれば概ね正確に掴むことができます。
直接作業時間は、製造業を例にとると段取り時間プラス加工時間です。勤務時間から休憩時間を除いた時間が就業時間ですが、そこには手待ち時間、間接作業時間が含まれています。
この製品を製造するために使った時間と分かる時間が直接作業時間です。加工因数が分かれば、全社的に使っている直接作業時間は概ね正確に掴むことができるはずですし、実績を取るという方法もあります。
製品の収益性判定モデル
次に、全社的目標となる1時間あたり付加価値を算出した方法と、同じことを製品ごとに行います。
販売価格から材料費と外注費を控除すると、その製品の付加価値が分かります。そして、この付加価値をその製品を製造するために費やした直接作業時間で割って、その製品の1時間あたり付加価値を算出します。各製品の付加価値の合計が全社的な付加価値になるという関係にあります。また、各製品の直接作業時間の合計が全社的な直接作業時間です。
そして、各製品の1時間あたり付加価値を、全社的目標となる1時間あたり付加価値と比べることで、各製品の収益性を判定定します。
また、全社的な1時間あたり付加価値とは別に、1時間あたり損益分岐付加価値も算出しておきます。最低限確保したい1時間あたり付加価値の目安になります。具体的には、利益をゼロとして逆算して、損益分岐付加価値を求めます。その上でこれを直接作業時間で割って、1時間あたり損益分岐付加価値を算出します。
収益性の判定は、全社的目標となる1時間あたり付加価値と、損益分岐となる1時間あたり損益分岐付加価値を判定のものさしとして、各製品の収益性を判定します。
具体的には、黄色のラインを超えている製品は収益性が良好な製品であり、積極的に増やしていきたい製品。黄色のラインには届かないものの赤いラインが超えている製品は、収益性が物足りない製品で収益性改善を図りたい製品。赤いライン以下の製品は、収益性が悪く抜本的な改善が煮込めない場合には切捨ても検討して、その生じた余力を収益性の良い製品に投下していくという戦略も有効になってきます。
具体例
次は、具体的に数値を当てはめておさらします。
例えば、目標利益が500で固定費が500の企業があったとします。この場合、目標付加価値は目標利益から逆算して500+500で1000になります。
そして、この目標付加価値1000に対して加工員の数と稼働時間などを考慮して、全社で100時間の直接作業時間を製品の加工に当てることができると考えます。この場合、全社的目標となる1時間あたり付加価値は、目標付加価値1000を直接作業時間100で割って10と求められます。
つまり、1時間あたりの加工で10の付加価値を生み出せれば、目標利益が達成されるという意味です。この10が1つ目のものさしとなります。
次に、利益を0と置くと損益分岐付加価値は500です。
そして、損益分岐付加価値500を投下できる直接作業時間100で割ると、損益分岐となる1時間あたり付加価値は5と求められます。これは、1時間あたりの加工で5の付加価値を生み出す製品だけだとちょうど利益が0になるという意味です。つまりそのような製品ばかりだとギリギリ赤字にはならないものの、目標利益は達成されません。この5が2つ目のものさしです。
今度は各製品の収益性を算出します。例えば、販売価格が500で変動比率が36%の製品の場合、付加価値は320です。この製品に40時間の直接作業時間を投下している場合、1時間あたり付加価値は320÷40で8です。これを、先ほどのものさしと比べることで製品の収益性の良し悪しを判定していきます。
1時間あたり付加価値8の製品は、黄色のライン10には届きませんが、赤いライン5は超えています。赤いライン以下の製品は、抜本的な改善を測る余地がない場合には切り捨てを検討すべきですが、製品Aはそれよりは収益性は良いものの収益性が物足りない製品で、収益性の改善を図り黄色のラインを超えたい製品と言えます。このように、具体的なものさしを持って製品を判定すると、改善目標が明確になって改善欲の向上にもつながります。
明確な目標があると頑張れるというのは人間の持つ性質です。
また、改善のポイントを探る際に利益構造が役に立ちます。1時間あたり付加価値を上げるためには、仕入れ価格を下げる、販売価格を上げる、あるいは生産性を上げることが考えられます。生産性を上げるとは、少ない時間で加工できるように効率化するという意味です。このように整理して、どこに改善の余地が大きいのか特定して、集中的に改善を図ることが効果的です。
ここでは製造業を例に取りましたが、他の業種でも売上高から変動費を控除したものが付加価値になるという構造は同じです。このように、自社の利益構造を整理して全社的目標となる1時間あたり付加価値、1時間あたり損益分岐付加価値を算出して、それらをものさしとして各製品の収益性を判定してみると意外な気づきがあるかもしれません。
まとめ
それでは、本日のまとめです。
まず、収益性の判定は漠然とした判定ではなく、具体的なものさしを持って判定することが、具体的な改善につながり重要という話をしました。そして、そのものさしとは全社的目標となる1時間あたり付加価値、1時間あたり損益分岐付加価値の2つであることをお伝えしました。
判定後は、結果に従って戦略を考えます。収益性の良い製品は重点製品として積極的に推進し、そうでないものは改善を図ります。あるいは、思い切って切り捨てて余力を生み出し、優点商品に余力を投下する戦略も有効です。そして何より、改善目標が明確だと人は頑張れます。
是非、自社のものさしを作って増収増益を実現していただきたいと思います。
講師に無料相談をする
ビジネス処方箋に登壇している講師に無料相談を行うことができます。
お問い合わせいただきましたら、ご相談内容に適した士業・経営者の講師をご紹介いたします。