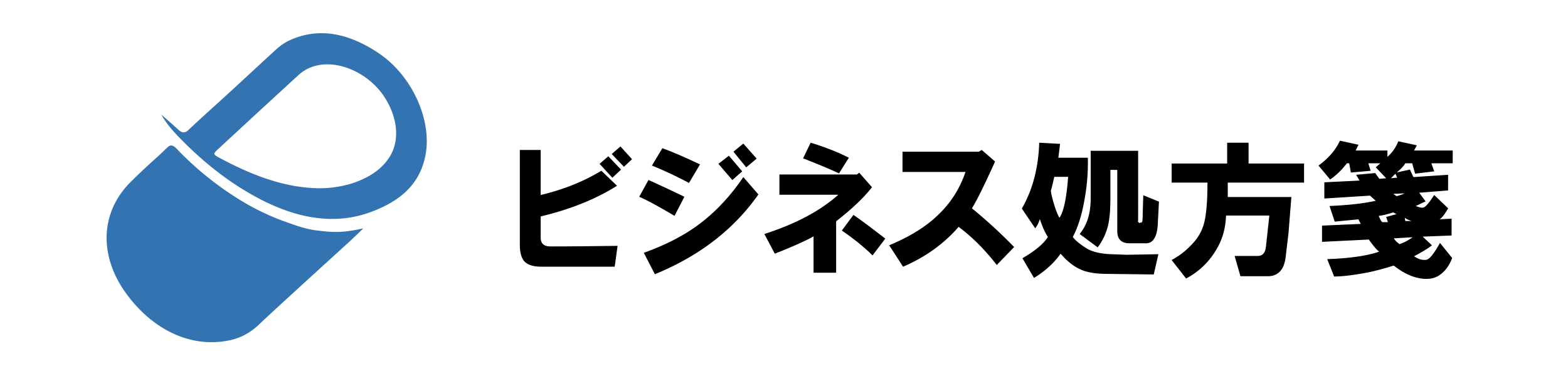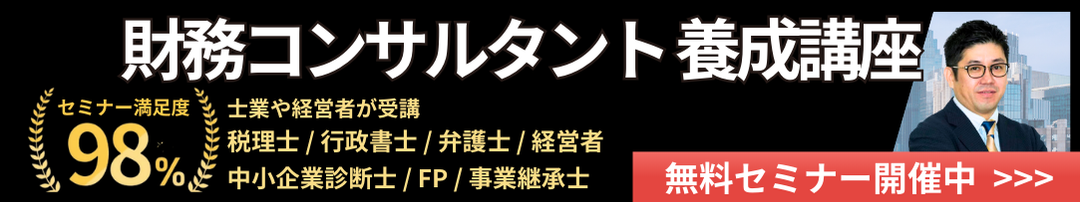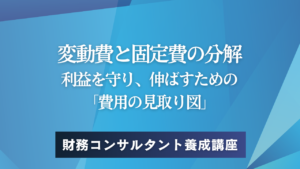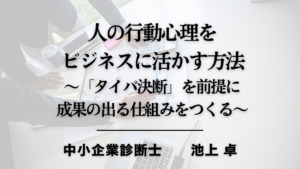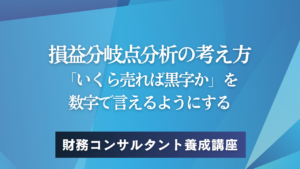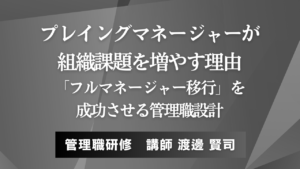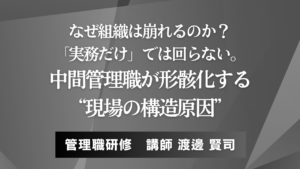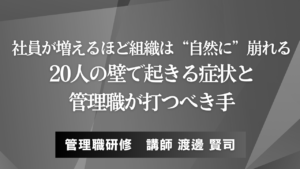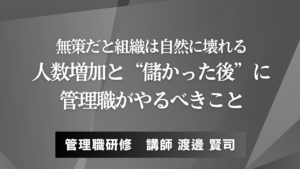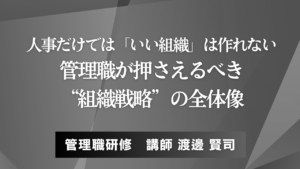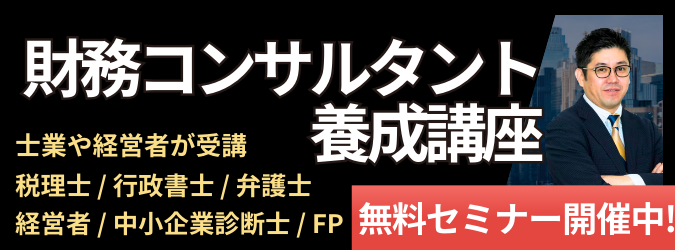中小企業が活用すべき短期継続融資とは?

池谷 卓
中小企業診断士
約30年以上にわたり、素材メーカーに勤務し、国内外の生産設備・ライン
設計・保全や生産拠点運営、新事業開拓、経営企画、DX推進等を経験。2023年に中小企業診断士として登録。
はじめに
多くの企業経営者は、『利益、収益をあげ会社を継続させる』ためには『資金繰りを安定させる』ことが重要であることを知っています。それは会社が成長し存続するために継続的に利益を上げていくことは重要なことだが、資金繰りが破綻すればそれこそ黒字倒産の憂き目にあうことを知っているからです。
資金繰りを破綻させないためにはファクタリングやエクイティファイナンスなどもありますが、やはり一般的なものは銀行からの融資になります。その中でも短期継続融資は中小企業にとって活用する価値のある手段であると言えます。今回はこの短期継続融資の背景から、融資利用に関するポイントや銀行との付き合い方などについてご紹介します。
短期継続融資の基本
金融システムと金融機関動向
1990年代後半の不良債権問題で揺らいだ金融システムにおいては、運転資金融資にも関わらず証書貸し付けで約定弁済を求める金融機関も存在しました。そのため、折角資金繰り悪化の対策として融資を受けても、期待したキャッシュバランスの改善がされずに結果的にさらに融資を重ねることとなることや、売上拡大のために設備調達をしても運転資金の調達がままならないなど、中小企業のニーズを合わないなど融資が行われることもありました。しかしその後、金融庁が融資先の『事業評価に基づく円滑な資金供給』を目指すべきと大きく方針転換を行ったことで、それらニーズの受け口として短期継続融資が注目を浴びることとなりました。この方針転換は、少子高齢化社会などにより日本経済は安定成長するばかりではない中では、金融機関は従来的融資活動だけでなく、融資先の事業評価に基づきリスクをとった融資活動を行い中小企業活動の活性化、国内経済の活性化に貢献すべきであることを意味しています。
もちろん、だからと言って短期継続融資に対してすべての金融機関において同じように対応しているわけではなく、中には短期継続融資を取り扱わないところや引き受けたとしても経営者保証や担保を求められるケースは存在します。
短期継続融資の概要
短期継続融資は金利分を差し引いた残りを融資として受けて期日に一括返済する融資あることから、証書貸し付けとは違いキャッシュバランスを改善することが期待できます。実際の運用では、期日になると再び同様な形式の短期融資を受けて書き換えて手続きを繰り返す融資方法で、この点から短期転がし(短コロ)とも呼ばれています。
また短期継続融資は定期的な返済を求められずに金利だけを支払えばよく、実質的に金利負担だけで継続的に借り続けられることから、融資の効果を最大限に享受でき長期的に資本に似た性質があります。
これらの点から運転資金を充足したい中小企業にとっては、使い勝手が良い融資と言えます。また銀行側としては、安定した利息収入を得ることや柔軟な資産運用などによるリスク分散、顧客との長期的・定期的な関係性維持などのメリットがあります。
デメリットとしては支払い期限延長を拒否や更新を拒否される、元々高めの金利をさらに上げられるなどにより、借り手である中小企業の資金繰りが急激に悪化する場合があることです。短期継続融資は、更新の際に企業の業況や実態を適切に評価、つまり事業性評価を行うことで継続の可否などを判断する運用がなされていることから、このようなデメリットが存在します。
短期継続融資の利用場面
短期継続融資の主な利用場面は、企業が営業活動を継続するために必要な資金である運転資金が不足する場合です。具体的には売掛金の回収遅れや季節変動のある業種の場合の一時的な売上増に対応する運転資金不足、在庫調整、事業拡大時の一時的運転資金不足など、売上債権、棚卸資産、買い入れ債権による資金不足の場面などになります。
短期継続融資におけるポイント
申請に必要な書類とポイント
銀行から融資を受けるために必要な書類は金融機関や融資条件などによって異なりますが、一般的な書類としては以下の様なものになります。金融機関はこれらの書類を総合的に分析して融資を出すかどうかの判断をすることになります。
1. 財務諸表(損益計算書、貸借対照表など)
当たり前ですが金融機関は返済できる企業にしか融資しないので、損益計算書において経常的に利益が出ているのか事業活動によって返済に必要な利益を生みだせているのかなどを評価しています。そして、それに加えて貸借対照表や事業計画書などを総合的に判断して事業の継続性や将来性、財務的な安定性、企業体力についても評価をしています。
また、そもそも損益計算書と貸借対照表に虚偽や間違った部分がないのか、例えば、売掛金や棚卸資産、貸付金の流動性や棚卸在庫増や償却不足による利益のかさ上げ、売上と相関性のない運転資金、負債と相関性のない金利負担、建設進捗操作による利益などによる粉飾有無などの財務実態評価を行っています。金融機関によっては軽微な粉飾の場合には公にしないこともあるようですが、酷くなると融資は不可能になりますし、すでに融資した分の一括返済を求める場合もあります。
2. 試算表
月次で作成する試算表では、直近の財務状況など直近決算から変化している状況を評価します。
3. 資金繰り表
資金繰り表によりキャッシュの流れを把握しどのタイミングで資金不足になるのか、また営業活動から返済のため資金を生み出せるのか、さらに取引先の取引条件の変化が資金繰りに与える影響の有無などの評価をします。
中小企業の中には作成した経験がない場合もあり、金融機関が作成する場合もあるようですが、提出する資金繰り表は信用保証協会が求めるものよりも詳細なものを求められます。
4. 事業計画書
融資先の事業内容や社内環境(強み・弱み)、社外環境(機会・脅威)、ビジネスモデル、それを実現のための計画を理解して事業の成長性や融資返済の能力などについて評価します。
5. 銀行取引一覧
他の銀行の融資残高、預金残高など取引を確認することで、他銀行からの信頼性なども理解できることから財務安定性や融資リスクを判断します。
6. 納税証明書
金融機関によって提出する納税証明書に違いはありますが、法人税、消費税などの納税義務を果たしていることを証明するものであり、金融機関では滞納による融資リスクの有無を評価します。
7. 商業登記簿謄本など
企業の基本的な情報を確認します。
金融機関との関係性構築・維持
名前も顔も知らない人からお金が必要なのでお金を貸してほしいといわれたら、多くの方はお金を貸すことはないと思います。同じように金融機関も経営者や従業員、事業内容、事業状況などをよく理解していない企業への融資は難しいのです。
そのため、中小企業側から定期的な情報交換や挨拶などを積極的訪問することが大事になります。それに加えて、金融機関側が企業を定期的に訪問する機会を活用して事業や将来の資金利用などに関する情報交換をすることも大事です。金融機関側は提出書類だけではなく中小企業と真摯に向き合ってコミュニケーションを図りたいのだと考えて、積極的なコミュニケーションを図るべきと思います。
現在は働き方改革や少子高齢化などの影響によりコミュニケーションに制約が生じやすいこともあるので、中小企業側からの積極的な関係性構築、維持、向上を図ることは非常に重要なことなのです。
まとめ
以上、短期継続融資についてその背景にある金融システムの動向や短期継続融資の概要、その活用に関するポイントなどをご説明しました。説明の中でも述べましたが、短期継続融資は各金融機関で取り組みが違うことに加えて事業性評価が融資可否に与える影響が大きいことから、ビジネスモデルやビジネスプランなどがしっかりした事業計画を立案行ったうえで金融機関との関係性の構築・発展などを進めることが重要になります。それらのことを戦略的に進めるためには、中小企業の経営に関する広く深い知見を持つ優秀な中小企業診断士に相談することも非常に有用だと考えますのでご検討ください。
今回のご説明が、皆様のビジネスに少しでもお役に立てば幸いです。