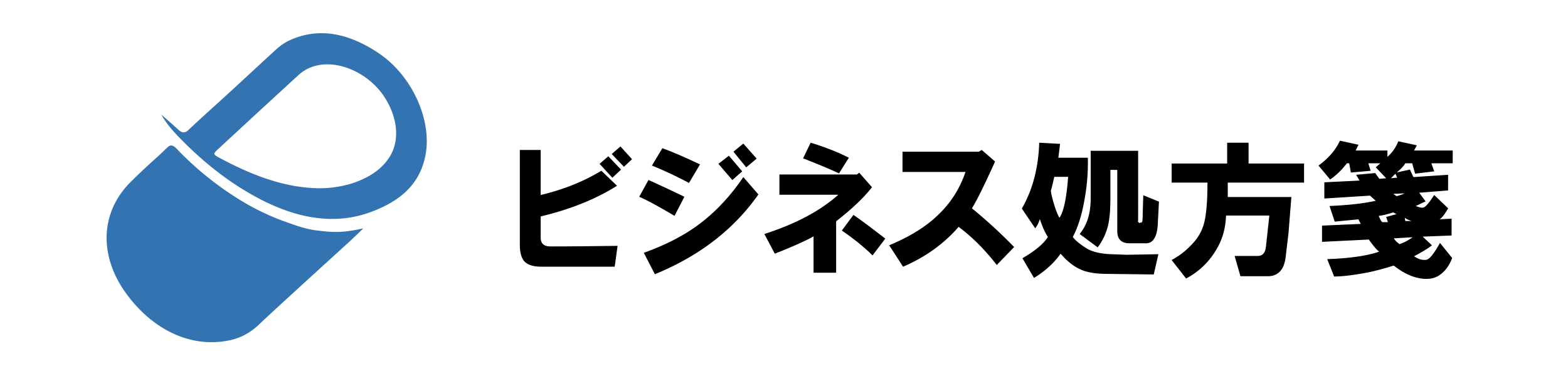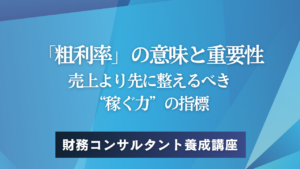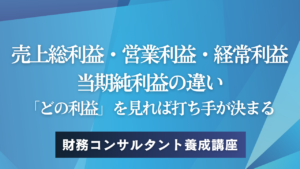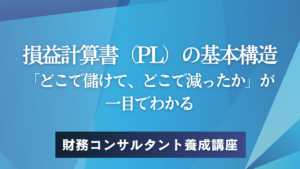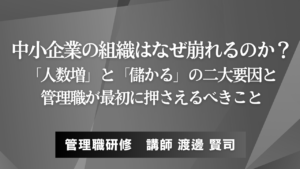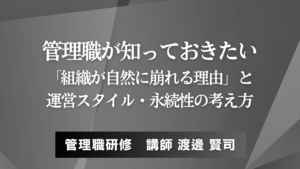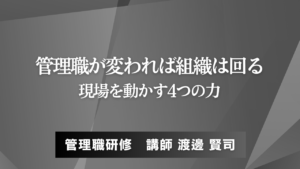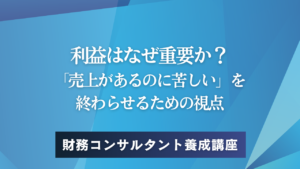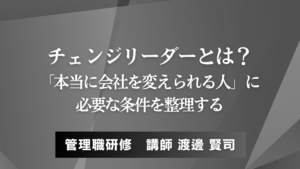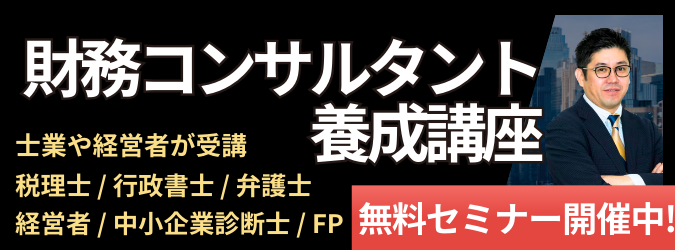知らないと危険!補助金不正受給の実態と重いペナルティ

伊藤 勝人
中小企業診断士
社オリジナル雑貨・軽家電製品の企画・開発・販売に携わり、主要顧客である小売店や通販事業者への営業活動を通じて、製品の市場導入から販路拡大までを一貫して担当。
複数の業界において、ホームページ運営やEC事業の立ち上げ・運営を手がけ、オンライン販売のノウハウを蓄積。企業のデジタルシフトを支援し、収益性の改善や効果的なマーケティング施策の立案に強みを持っている。
中小企業診断士として、企業の課題解決に向けたコンサルティング業務を行っており、実務経験に裏打ちされた現場感覚と、理論に基づく分析力を融合させた支援を提供している。
はじめに:補助金の不正受給とは
補助金は、事業者の成長や地域経済の発展を目的として、国や地方公共団体などの公的機関が支給する「返済不要の資金」です。これらの補助金は、適正に使われることを前提に支給されますが、実際には申請内容の虚偽記載や、経費の不正使用などによる「不正受給」が後を絶ちません。
不正受給の定義
不正受給とは、意図的に虚偽の情報を記載したり、制度の趣旨を逸脱して補助金を得たりする行為を指します。特に、「キャッシュバック」や「実質無料」などは不正行為の可能性があります。たとえ事業者側に悪意がなかったとしても、「制度の誤解」や「管理体制の不備」による結果として不正と見なされることもあるため、注意が必要です。
参考:IT導入補助金2025 不正の注意喚起
不正が発覚した場合のペナルティ
不正受給が発覚した場合、以下のようなペナルティが課されます。
- 補助金の全額返還
- 加算金や違約金の追徴
- 企業名・代表者名の公表
- 将来的な補助金申請の停止
- 悪質な場合は刑事告発(詐欺罪など)
つまり、一度不正が認定されると、金銭的な損失だけでなく、企業の信用や将来の事業展開にも深刻な影響を及ぼします。
2. 代表的な不正受給の例
架空取引・水増し請求
最も典型的な不正例が「存在しない取引の報告(架空取引)」や「実際より高い金額での請求(水増し)」です。たとえば、取引先と共謀して架空の請求書を発行し、補助金を不正に受け取るといったケースです。
対象外経費の流用
補助金には使用目的が細かく規定されており、それに反する使用は不正受給に該当します。
- 補助対象外の人件費や接待費に使う
- 事業と無関係な自社の家賃や通信費に充てる
- 家族や知人の私的な支出に補助金を流用する
完了報告書の虚偽記載
補助金は、事業完了後に「完了報告書」を提出し、実際に使用した経費や実績を報告します。この報告書に虚偽の情報(未購入品を購入したように記載など)を記載することも、不正行為に該当します。
事業未実施の補助金申請
申請時点ではやる意思があるように装いながら、実際にはまったく事業を実施せずに補助金だけを受け取るケースもあります。これは非常に悪質な詐欺行為として扱われます。
3. 実際の不正受給事例(ニュース・裁判例)
補助金制度は本来、事業の健全な成長を支援する目的で用意されていますが、残念ながら制度を悪用する事例も後を絶ちません。以下に、実際に発覚した代表的な不正受給事例をいくつか紹介します。
中小製造業A社の不正受給(経営革新支援補助金)
ある部品製造業の企業(以下、A社)は、「中小企業経営革新支援対策費補助金」を活用し、約1,020万円の補助金を受給していました。しかし、社内からの内部通報をきっかけに調査が行われた結果、架空請求を含む不正な申請が明らかに。関係者は逮捕され、補助金は全額返金。さらに、同社には今後30か月間の補助金交付停止処分という厳しい措置が取られました。
架空経費や水増し請求による不正
補助金申請の際、経費の金額や内容を偽る手口も多く見られます。たとえば、外注費を実際の50万円から100万円に引き上げて、虚偽の請求書を作成し申請するケース。または、実際には実施していないセミナーや研修の費用を計上し、補助対象経費として申請するといった例もあります。
個人事業主による設備投資の偽装
補助金は法人に限らず個人事業主も対象ですが、そこにも不正のリスクは潜んでいます。あるケースでは、設備投資を行っていないにもかかわらず、架空の請求書や領収書を用意して補助金を申請。たとえば、IT導入補助金において「ITツールを導入済み」と虚偽の内容で申請し、実際には何の導入もしていないにもかかわらず補助金を受給していた事例が報告されています。
コンサルタントが関与した不正スキーム
一部のIT導入補助金では、コンサルタントや登録ベンダーが主導となり、企業側と結託した不正が行われた例もあります。たとえば、実際には納品されていないシステムを「導入済み」と偽って申請書類を作成し、補助金を受給するよう指導。また、企業側が本来負担すべき自己負担分を、後からコンサル側がキックバックで補填し、実質的に全額補助金で賄うという不正が発生しました。
福岡市内のある美容関連企業では、申請のために偽の売上資料や通帳コピーが用いられ、コンサルタントが全面的に申請手続きを代行していたことも明らかになっています。
4. 不正が起きやすい背景と理由
補助金の不正受給は、単に「悪意を持った人が制度を悪用する」という単純な構図だけではありません。制度そのものの複雑さや、申請者側の知識不足、さらには不正を助長する第三者の存在など、さまざまな要因が絡み合って発生しています。ここでは、主な背景を3つの観点から解説します。
補助金制度の複雑さ
補助金制度は、目的や管轄する省庁・自治体によって内容やルールが大きく異なります。申請書類の作成から交付決定後の実績報告まで、求められる作業は煩雑かつ専門的であり、事業者がすべてを自力で正確に理解・対応することは容易ではありません。
特に、補助対象経費の範囲や、申請時・報告時に必要な証拠書類の要件は細かく規定されており、少しのミスや誤解が「不適正」あるいは「不正」と判断されるリスクにつながります。この制度の複雑さが、不正の温床となるケースも少なくありません。
小規模事業者の理解不足
小規模事業者では従業員数が限られているため、経理・総務の専任者がいないか、兼任しているケースが多く見られます。そのため、制度内容やルールの確認に十分な時間や注意を割くことができません。
申請や経理処理に誤りがあっても気づけないリスクが高まります。
悪質なコンサル・業者の関与
悪質業者は、補助金申請の支援を装って事業者に虚偽申請をそそのかし、交付対象にならない支出を、あたかも対象経費であるかのように合法的に見えるよう工作します。
具体的には以下のような手口があります。
- 「実質無料」や「返金します」と勧誘し、企業負担をゼロに見せかける
- 導入していない設備やITツールを「導入済み」と虚偽報告させる
- 申請書類や見積書を偽造して、不正に補助金額を引き上げる
- 自社にキックバックさせる契約を事業者に強要する
5. 不正受給のリスクと影響
返還命令・罰金・刑事告発
不正が判明した場合、補助金の全額返還だけでなく、違約金や加算金、さらには刑事責任(詐欺罪、文書偽造罪など)を問われることもあります。補助金で得た利益どころか、大きな損失につながることも珍しくありません。
| 項目 | 対象者・行為 | 罰則内容 | 備考 |
| ① 不正受給・不正融通 | 偽り・不正な手段で補助金や間接補助金を受けた者 | ・5年以下の懲役刑 ・100万円以下の罰金 ・または併科 | 嘘の申請書類、架空取引等による不正受給も含む |
| ② 不正交付への関与 | 不正を知りながら交付・融通を行った者 | ・①と同じ(懲役刑または罰金) | 知っていて協力した者も同罪 |
| ③ 目的外使用 | 補助金・間接補助金を用途外に使用した者 | ・3年以下の懲役刑 ・50万円以下の罰金 ・または併科 | 例:人件費目的の補助金を設備投資に流用など |
| ④ 報告義務違反等 | 報告義務違反・虚偽報告・検査拒否・虚偽答弁など | ・3万円以下の罰金 | 軽微な違反行為に適用 |
| ⑤ 両罰規定(法人等) | 違反行為を行った者の所属法人または事業主 | ・違反者個人に加え、法人 ・事業主にも罰金刑 | 組織ぐるみで処分される可能性あり |
| ⑥ 公務員の違反行為 | 国・地方自治体の職員が違反行為をした場合 | ・行為者個人に対し、各条の刑を科す | 国・自治体は対象外、職員個人に責任が及ぶ |
参考:厚生労働省 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
信用失墜・取引停止
公的支援を受ける立場の企業が不正を行うと、社会的な信用が大きく失われます。自治体のホームページなどで企業名が公表されることもあり、取引先からの信用も一気に失う可能性があります。
将来の補助金申請不可
一度不正が認定されると、その企業や代表者は将来的に補助金・助成金の申請自体ができなくなる場合があります。これは、今後の事業展開において致命的なデメリットとなり得ます。
6. 不正防止のためのチェックポイント
経費管理体制の整備
補助金の使用状況を常に記録し、管理できる体制を構築することが重要です。社内に経理担当がいない場合は、会計士や税理士と連携し、透明性の高い経費管理を行いましょう。
書類保存・管理ルールの徹底
領収書や契約書などの証憑は、補助金ごとに保存期間が異なりますが、最低でも5年間は保存する必要があります。補助金ごとに求められる保存期間・書類も異なるため、初期の段階でルールを定め、担当者を明確にしておくことが望まれます。
外部専門家の相談
制度の内容を正確に理解し、正しく申請・運用するには、補助金に詳しい専門家(中小企業診断士、行政書士、税理士など)に相談するのが効果的です。初期段階から関与してもらうことで、リスクを未然に防ぐことが可能になります。
7. 専門家に相談するメリット
予防相談・事後対応のアドバイス
専門家に相談することで、補助金の使い方が適正かどうか、事前にチェックを受けることができます。また、仮に問題が発生した場合でも、適切な是正方法や対応策のアドバイスを受けられます。
コンプライアンス強化の支援
申請書類の作成から経費管理、報告書の作成に至るまで、プロの目線で支援を受けることで、コンプライアンス意識の高い経営が実現できます。結果的に、補助金以外のビジネス面でも信用力の向上につながるでしょう。
8. 【まとめ・無料相談案内】安心・安全な補助金活用のために
補助金は、正しく活用すれば事業成長の大きな助けになります。しかし、制度の複雑さや管理の不備により、知らず知らずのうちに「不正受給」とされてしまうリスクも存在します。
不正受給を避けるためには、
- 制度の理解
- 適切な書類管理
- 専門家への相談
が不可欠です。
補助金の活用を検討中の方、不安を感じている方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。無料相談を活用すれば、リスクなく安心して制度を利用できます。
公正・透明な補助金活用こそ、事業の未来を拓く第一歩です。