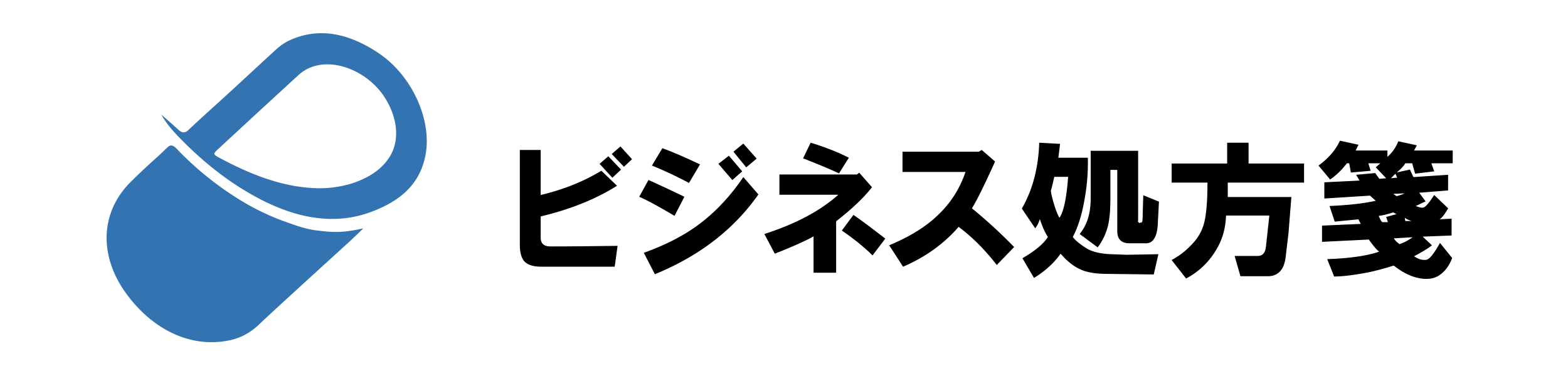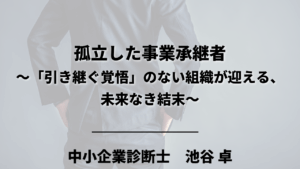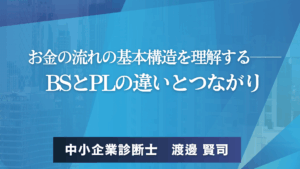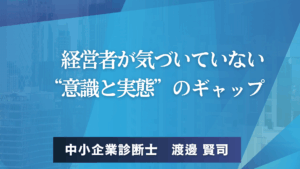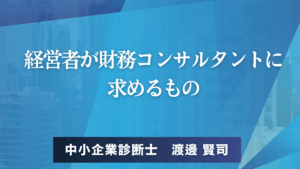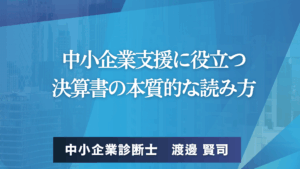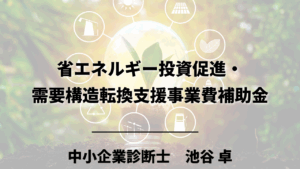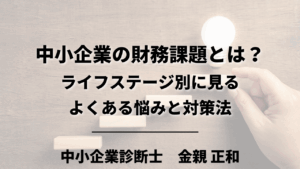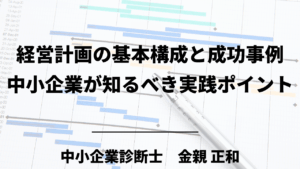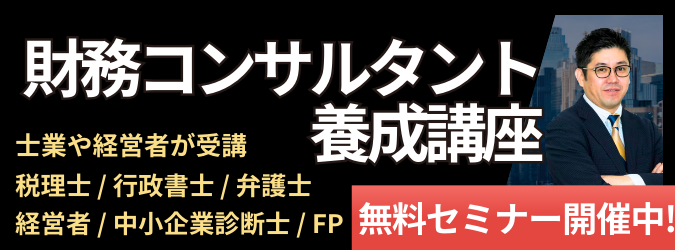中小企業向けの投資育成制度とは? メリット・デメリットも解説!!

金親 正和
中小企業診断士
中小企業診断士 / 宅地建物取引士 / 不動産コンサルティングマスター
賃貸不動産経営管理士 / 管理業務主任者 / 防災士
大学卒業後、総合不動産会社にて不動産の企画・開発、賃貸物件のリーシング・管理(5,000室)、売却(半年間で46物件)と入口から出口までの業務に従事。
現在は、「補助金を通じて、中小企業経営者の皆様を支えたい」という思いから、各種補助金の申請支援に注力している。
投資育成とは
投資育成とは、「中小企業投資育成株式会社法」という法律に基づいて、中小企業投資育成株式会社が投資や研修などを行い、中小企業の成長発展を支援する制度です。
中小企業投資育成制度は、資本金3億円以下の株式会社、またはこれから設立しようとする方を対象にしています。
その他、以下の法律に基づく特例による新規の投資については、資本金が3億円を超えるものであっても投資の対象となっています。
- 中小企業労働力確保法
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
- 中小企業地域資源活用促進法
- 新エネルギー利用の促進に関する特別措置法
- 大学等技術移転促進法
- 中小企業経営強化法
- 中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律
- 農林漁業バイオ燃料法
- アジア拠点化推進法
- 下請中小企業振興法
- 産業競争力強化法
- 中心市街地活性化法
- 地域未来投資促進法
- 生産性向上特別措置法
投資育成では、事業規模や経営状況に応じて資金援助を受けることができます。
具体的には、中小企業投資育成株式会社(以下、投資育成会社)が企業に出資する形で、成長をサポートします。
この制度の背景には、日本経済の基盤である中小企業を支援し、地域経済や雇用を維持・拡大する目的があります。投資育成会社は、国が主体となり設立され、特定の地域を中心に中小企業の支援を行います。
| 項目 | 内容 | 詳細説明 |
目的 | 中小企業の成長を支援し、経営基盤を強化する | 中小企業が持続可能な成長を実現するための資金提供や経営支援を実施 |
対象 | 主に安定した経営基盤を持つ中小企業 | 資本金3億円以下または特定の法律に基づく特例による新規投資を行う場合は資本金が3億円を超える株式会社も対象 |
支援内容 | 資金提供や経営支援、税制優遇措置など | 出資による経営の安定化、事業承継支援、後継者育成。また、経営に関する助言やコンサルティングサービスも提供 |
特徴 | 国が関与し、長期的な成長を目指した支援 | 長期的視点に基づく出資支援、経営の自主性を尊重し、株式上場や役員派遣、経営干渉なく後方支援であること |
メリット | 安定的な資金調達、信頼性の向上 | 出資による資金調達に返済義務がないこと公的機関が株主になることで対外信用力が向上 |
デメリット | 手続きが複雑、株式譲渡による経営自由度の制約 | 書類提出や審査が煩雑で、申込から投資を受けるまで通常3ヶ月程度。また、株式譲渡により配当の実施、株主総会の開催・投資育成会社による出席、決算報告など経営に一定の制約が生じる可能性がある |
投資育成とベンチャーキャピタルの違い
投資育成については、上述したとおりですが、ベンチャーキャピタル(VC)についても簡単に説明します。
ベンチャーキャピタルとは、高成長が期待されるスタートアップ企業に対して資金を提供して、経営支援を行う投資機関です。
創業初期や成長初期の企業を対象として、リスクを伴うものの、高いリターンを狙います。単なる資金提供にとどまらず、経営戦略やネットワーク構築、人材採用支援など幅広いサポートを提供します。
出資比率が高いため、経営に積極的に関与することが多く、投資後の企業価値向上を目指します。投資額は数千万円から数十億円規模に及ぶこともあります。
このとおり、投資育成とベンチャーキャピタル(VC)は、どちらも企業への資金提供を通じて成長を促進しますが、その目的や対象となる企業、運営の方針にいくつかの違いがあります。
| 中小企業投資育成 | ベンチャーキャピタル | |
| 目的 | 安定的な成長 | 高リターンを狙った成長 |
| 対象 | 安定的な中小企業 | スタートアップ企業 |
| 保有方針 | 長期安定株主・安定配当株式上場は義務付けない | 3~5年で投資回収株式売却によるキャピタルゲイン |
| 経営への関与 | 自主性を尊重 | 積極的な関与 |
| 支援内容 | 資金提供や経営支援、事業承継支援 | 資金調達や経営支援、人材紹介、株式上場支援など |
1. 投資対象の企業段階
投資育成: 成熟した中小企業が対象。事業が安定しており、さらなる成長を目指す段階の企業に適しています。
ベンチャーキャピタル: 創業初期や成長初期のスタートアップ企業が中心。革新的なアイデアや技術を持つ企業にリスクをとって投資します。
2. 投資スタイル
投資育成: 比較的低リスクで安定した運用を目指します。出資比率は通常少数にとどまり、経営に直接関与しないケースが多いです。
ベンチャーキャピタル: 高リスク・高リターンを狙い、大規模な投資を行い、経営に積極的に関与することが一般的です。
3. 支援内容
投資育成: 長期的な視点で経営の安定化を図り、企業価値を向上させます。また、事業承継時の納税優遇制度などの税制優遇措置が利用できる点も特徴です。
ベンチャーキャピタル: 資金提供だけでなく、マーケティング、事業戦略、人材採用、上場支援など幅広い支援を行います。
投資育成のメリット
投資育成制度活用のメリットについては、上段でも記載していますが、主には以下の4つに集約されます。
1. 安定的な資金調達
投資育成会社からの出資は長期的な視点で行われるため、自己資本の充実や資金繰りが安定します。返済義務のない資金であるため、企業は負担なく成長戦略を実行できます。
2. 円滑な事業承継
投資育成会社への第三者割当増資を行うことにより、自社株評価額が低下し、円滑に事業承継を進めることができます。
3. 信頼性の向上
国が関与している制度であるため、投資育成会社からの出資を受けた企業は社会的信頼度が向上します。この信頼性は、取引先や金融機関との関係構築にもプラスに働きます。
4. 後継者の育成
経営全般における相談ができ、各種セミナーやビジネススクールが用意されています。経営者の会もあり、交流の場を通じて人脈形成や取引先拡大にも繋がります。
投資育成のデメリット
投資育成のデメリットについても、上段でも記載していますが、主には以下の3つに集約されます。
1. 出資による制約
投資育成会社の出資を受ける場合、一定の株式を譲渡する必要があります。これにより、株主構成が変わり、配当の実施、株主総会の開催・投資育成会社による出席、決算報告など、経営の自由度が一部制約される可能性があります。
2. 投資対象の制約
投資育成会社は、基本的に中小企業を対象としているため、業種や規模によっては適用外となる場合があります。
3. 必要書類や手続きの複雑さ
投資育成制度を利用するには、多くの書類提出や審査を通過する必要があります。法律に基づき実施される制度のため、時間と労力がかかり、企業の負担となることがあります。
投資育成に向いている会社
投資育成を利用する条件がありますが、その条件に合致する企業は向いていると言えるのではないでしょうか。
<条件>
- 原則として資本金3億円以下の株式会社であること
- 事業基盤があり安定的な配当を実施できる収益力を有していること
- 公序良俗に反しない企業、投機的な事業を行っていない企業であること
引用:制度活用をご検討の皆様へ|東京中小企業投資育成株式会社(SBIC)
1. 安定した経営基盤を持つ企業
投資育成制度は、安定した事業運営を行い、今後さらなる成長を目指す企業に適しています。過去の業績や財務状況が良好であることが重要です。
2. 長期的な視点で成長を考える企業
短期的な利益ではなく、長期的な成長を目指す企業にとって、この制度は大きなメリットがあります。株式をめぐるトラブルや後継者不在などの課題をもっている企業においても、事業承継を円滑に行うことができるので、安心して持続的な事業運営が可能になります。
まとめ
投資育成制度は、安定した経営基盤を持つ中小企業にとって、成長のための有力な手段です。ベンチャーキャピタルとは異なり、低リスクで安定した支援を受けられる点が特徴です。
投資育成制度を活用して、安定的な資金調達、円滑な事業承継、有益な後継者育成により、あらゆる方面からの信頼性も向上することでしょう。
本制度を活用する際には、事業計画書や収支見通しの作成など様々な書類を準備しなければなりません。
公的機関が行うため、審査も厳しいものとなっていますので、ご検討されたい方は是非ご相談ください。