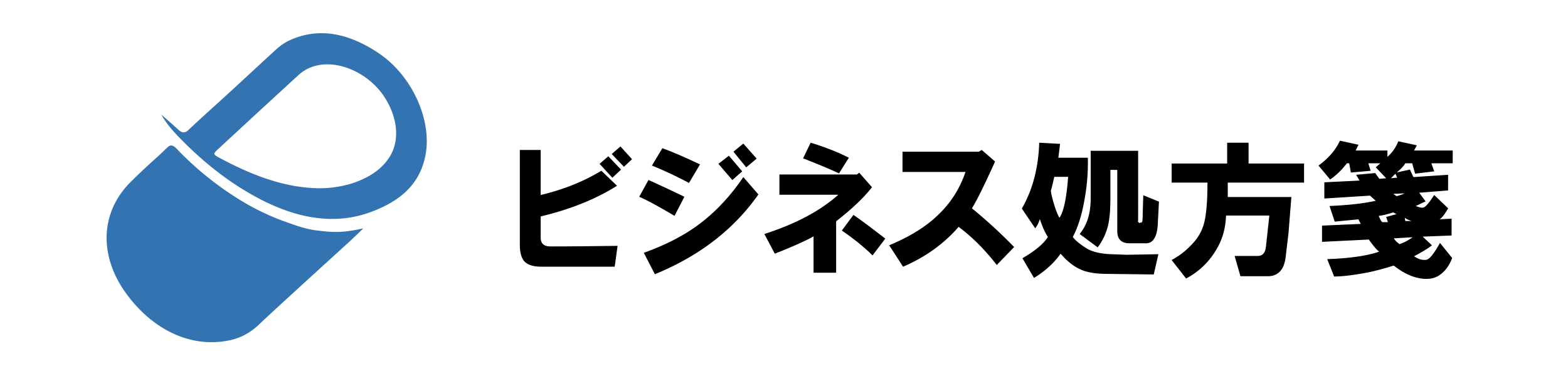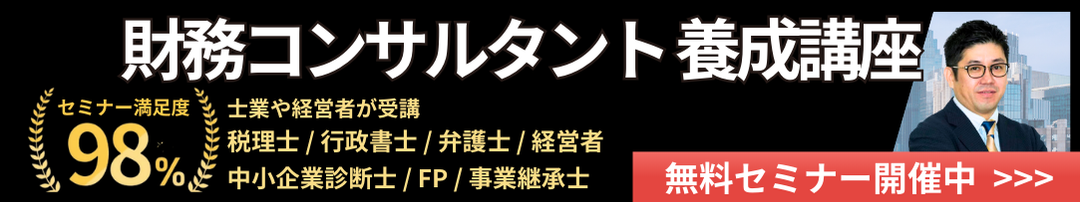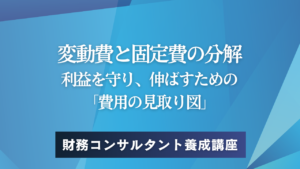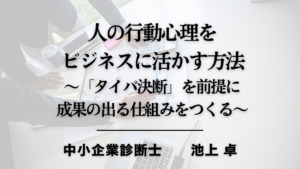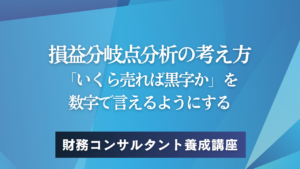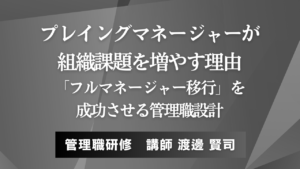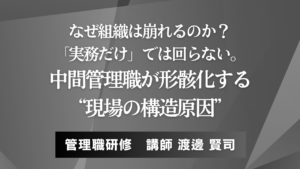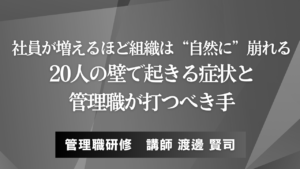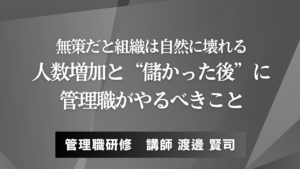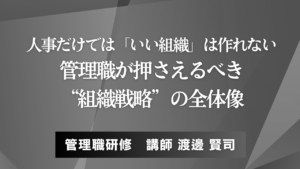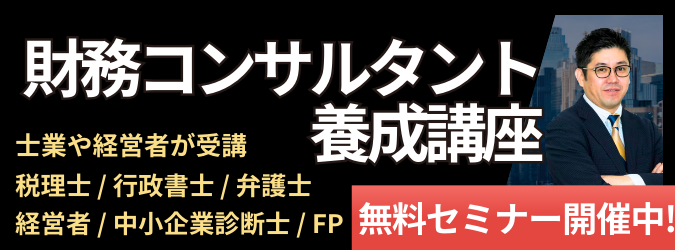「行政書士はやめとけ、意味ない」と言われる理由とは?実態と対策を解説
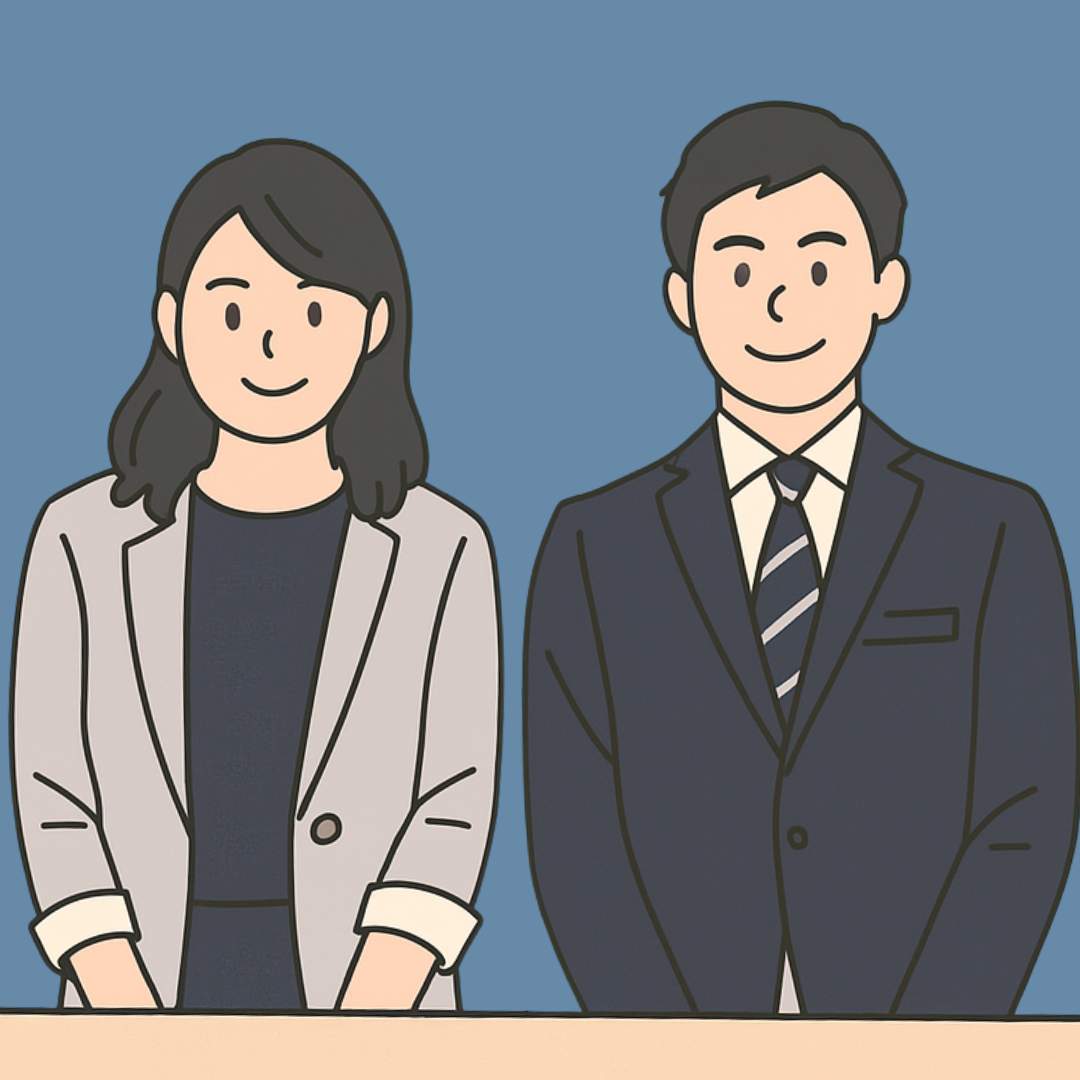
事務局
財務コンサルタント養成講座 運営事務局
2024年より講座を開講。これまでに税理士・行政書士・中小企業診断士をはじめ、保険募集人やIFAなど累計300名以上の専門家が受講。
財務支援/財務コンサルタントを目指す士業・コンサルタントの方に向けて、財務コンサルタントとしての実践ノウハウや働き方について情報発信を行っています。
なぜ「行政書士はやめとけ」と言われるのか?
「行政書士は意味がない」「きつい」「つらい」「やめとけ」——こうした否定的な言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
こうした声の背景には、以下のような要因が挙げられます。
- 資格取得者の増加による競争の激化
- 独立開業後の収入の不安定さ
- 独占業務の範囲が限定的に見えること
特に開業初期は、顧客の獲得が難しく、収入が安定しにくい時期が続きます。加えて、営業や経理、事務管理など、業務のすべてを一人でこなさなければならず、「思った以上に厳しい」という現実に直面する人も少なくありません。
しかし一方で、行政書士として高い専門性を磨き、他士業と連携しながら活躍している人も多くいます。適切な戦略と努力次第で、年収1,000万円以上を実現しているケースも珍しくないのです。つまり、厳しい一面がある一方で、やりがいと成功の可能性を秘めた資格でもあります。
「行政書士は意味がない」と言われる背景とは?
「行政書士はやめたほうがいい」「意味がない」といったネガティブな声には、いくつかの誤解や先入観が含まれています。
たしかに、行政書士試験の合格者数は年々増加傾向にあり、競争が激しくなっているのは事実です。しかし、行政書士の扱う業務は非常に多岐にわたり、1万種類以上とも言われる許認可申請の業務が存在します。つまり、実際には飽和状態とは言い切れません。
また、行政書士の収入も「低い」と一括りにはできません。独立開業している行政書士の平均年収はおよそ600万円程度とされており、分野によっては年収1,000万円を超えるケースもあります。これは、扱う業務の種類や地域、営業力などによって大きく異なるため、一概に「稼げない資格」と断定するのは早計です。
さらに、「行政書士の独占業務は範囲が狭い」とも言われがちですが、実際には次の3つの分野が行政書士に認められた独占業務です:
- 官公署に提出する書類の作成および提出代理
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
これらの中には建設業や飲食業、外国人の在留資格申請など、実務上需要の高い業務も含まれており、専門性を磨けば継続的な依頼も見込めます。
行政書士を目指すうえでは、こうした実態を正しく理解し、的確な準備と戦略を立てることが何より重要です。
行政書士の登録者数と現場の実情
行政書士の登録者数は年々増加しており、2023年時点でその数は5万人を超えています。行政書士試験には毎年4,000人〜6,000人が合格しますが、実際に登録する人はおよそ2,500人程度。つまり、試験合格者のうち約半数が登録・実務に進むという状況です。
一方で、同年には約1,700人が登録を抹消しており、差し引きで年間約800人の純増となっています。この増加ペースに対し、「行政書士が多すぎる」「飽和しているのでは」という声もありますが、実態は一様ではありません。
たとえば、鳥取県(215人)、佐賀県(262人)、高知県(263人)など一部地域では行政書士の数が相対的に少なく、地域によってはまだまだニーズを満たしきれていない現状もあります。
このように、全国的に見れば登録者数は増加傾向にありますが、地域別や業務分野別での需給バランスは大きく異なっており、「どこでも仕事がない」という状況ではないのです。
行政書士としての将来性を考えるなら、競合の少ない地域やニッチな専門分野に目を向けることが、安定した収入と活躍の場を広げる鍵となります。
行政書士の収入事情:平均年収と実態のギャップ
行政書士の年収は、働き方や業務内容によって大きく異なります。一般的には年収400万〜600万円程度とされ、厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag(日本版O-NET)」によれば、令和6年時点での平均年収は591万円。これは、給与所得者全体の平均年収(約460万円)を上回る水準です。
ただし、あくまでこれは平均値であり、実際には年収1,000万円以上を稼ぐ人もいれば、生活が苦しいレベルで収入が低いケースもあります。
たとえば、建設業許可申請や在留資格の手続きなど、専門性と需要の高い業務に特化すれば、年収700万円〜1,000万円以上も狙えます。一方、相談業務や低単価の業務が中心となると、年収が240万円程度にとどまることもあるのが現実です。
特に開業初年度の行政書士は、年収100万円〜200万円にとどまることも多く、軌道に乗るまでには3年ほどかかるケースが一般的です。その一方で、営業力や専門性を武器に成功している行政書士は、安定した顧客基盤を築き、高収益を得ています。
年収に大きな差が出る要因には、以下のような点が挙げられます。
- 扱う業務の種類(単価・難易度)
- 営業力・集客力
- 専門性の深さ
- リピート率と紹介による案件獲得
- 士業ネットワークや企業連携の有無
行政書士としての収入を安定・向上させるには、単に資格を取るだけでなく、戦略的に分野を選び、継続的な実務経験とスキル向上に取り組むことが不可欠です。
行政書士として独立開業する際の課題とは?
行政書士として独立・開業を目指す際、多くの人が最初に直面するのが「収入の不安定さ」です。特に開業初期は、顧客基盤がゼロからのスタートとなるため、一定の収入を得られるようになるまでに時間がかかります。生活費や事務所の運転資金をあらかじめ準備しておくことが重要です。
また、会社員とは異なり、自ら営業活動を行い顧客を獲得しなければなりません。ホームページの運営、SNSでの情報発信、異業種交流会への参加など、集客のための行動が不可欠です。加えて、営業・経理・労務・総務といった業務もすべて自分でこなす必要があり、業務効率の工夫や時間管理能力も求められます。
さらに、行政書士は弁護士・税理士・司法書士など他の士業とも業務範囲が重なる場面が多く、競争も激しいのが現実です。たとえば、顧問契約を結んでいる企業は、登記や税務も含めた“ワンストップサービス”を求める傾向が強く、行政書士単独で案件を獲得するには、明確な差別化や強みの打ち出しが不可欠です。
また、開業にかかる初期費用も想定しておく必要があります。たとえば以下のような費用が発生します:
- 行政書士会への登録料・入会金:20〜30万円前後
- 名刺・事務用品・印鑑の作成費
- ホームページ制作費や広告費
- 書籍・実務資料の購入費
- パソコン・プリンターなどの備品購入費
一般的には90万円〜150万円程度が開業初期費用の目安となります。自宅を事務所として開業するケースもありますが、それでも設備投資は避けられません。
このように、行政書士として独立するには、収入面・業務面・競争面の課題を総合的に乗り越える必要があります。だからこそ、事前に綿密な開業計画を立て、戦略的な準備を進めることが成功のカギとなるのです。
行政書士が扱う専門業務の範囲
行政書士の業務は非常に幅広く、大きく分けて次の3つが「独占業務」とされています。
- 官公署に提出する書類の作成および代理提出
- 権利義務に関する書類の作成および代理
- 事実証明に関する書類の作成および代理
これらに付随して、各種相談業務も行政書士の重要な役割です。
具体的には、以下のような業務があります:
- 建設業許可、飲食店営業許可、産業廃棄物処理業許可などの許認可申請代行
- 契約書、遺言書、内容証明、示談書などの法的文書作成
- 在留資格の取得、永住・帰化申請など、外国人関連の手続き
これらは、法的な知識と正確性が求められる業務であり、行政書士の専門性が発揮される領域です。特に、建設業や外国人関連業務などは報酬単価が高く、高収益に直結する分野といえます。たとえば、建設業許可申請では平均で12万円以上、在留資格認定証明書交付申請などの外国人手続きではさらに高単価になることも珍しくありません。
一方で、弁護士・税理士・司法書士など他士業が取り扱える業務もあり、業務範囲が重複する部分も存在します。たとえば、会社設立における定款作成は行政書士が担当できますが、登記は司法書士、税務は税理士の独占業務です。
そのため、他士業と連携して“ワンストップサービス”を提供する体制を構築することが、顧客満足度を高め、継続的な案件獲得にもつながります。
行政書士として高単価な業務を安定的に受注していくには、こうした専門分野の知識を深めると同時に、信頼できるネットワークを構築することが成功の鍵となるのです。
行政書士資格の難易度と合格までの道のり
行政書士試験は「中の下」程度の難易度と言われることもありますが、決して容易な試験ではありません。毎年の合格率は10%前後と低く、国家資格の中でも一定の難関とされています。
特に、法律の学習経験がない初学者にとっては、相応の学習時間と計画が必要です。合格までに必要とされる勉強時間はおよそ600〜1,000時間。たとえば、1日2.5時間勉強を続ければ約10カ月、1日3時間なら9カ月で到達できる計算です。
行政書士試験は、法令科目と一般知識科目の2つで構成されており、両方で一定の基準点を超える必要があります。特に重要なのが「行政法」と「民法」で、全体の得点配分の大半を占めるため、最も重点的な学習が必要です。
また、2024年度(令和6年度)からは、一般知識科目の出題内容が「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」へと改正され、より実務に即した内容が問われる傾向にあります。
さらに、試験には記述式問題も含まれており、単なる暗記ではなく、法的な論点整理や文章構成力も問われます。このため、学習にあたっては、インプットとアウトプットのバランスが重要です。
独学での合格も可能ですが、効率的に進めたい場合は、通信講座や予備校の活用も有効です。特に社会人や子育て中の方など、まとまった学習時間が取りにくい方にとっては、スキマ時間の活用と学習計画の立て方が、合否を左右する要素となります。
行政書士試験は誰でも受験可能であり、社会人・学生・主婦など幅広い層が挑戦しています。合格には、長期間にわたる学習を継続する「計画性」と、自分に合った勉強スタイルを見つける「戦略性」が欠かせません。
行政書士を目指す際に考えておきたいこと
「行政書士は厳しい」という声を耳にして、不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、行政書士には厳しさと同時に、多くの魅力も備わっています。
たとえば、
- 年齢や学歴に関係なく挑戦できる国家資格であること
- 独立開業しやすく、自由度の高い働き方ができること
- 長く現役で活躍できる“生涯資格”であること
などが、行政書士の大きなメリットです。
これらの特性を活かすためには、漠然と資格取得を目指すのではなく、「自分はどんな働き方をしたいのか」「行政書士としてどの分野で専門性を磨きたいのか」といった、キャリアプランの明確化が重要です。
目指す働き方によって、必要なスキルや準備すべき内容が大きく変わってくるため、自分に合った方向性を早い段階で見定めておくことが、学習のモチベーション維持にもつながります。
行政書士としての働き方の選択肢
行政書士の働き方は一つではありません。以下のように、個人のライフスタイルや志向に応じて多様な働き方が可能です。
1. 独立開業型(個人事務所)
行政書士の働き方で最も一般的なのが、独立開業です。試験に合格し、日本行政書士会連合会への登録を済ませれば、自宅でもオフィスでも、自らの事務所を開設できます。建設業許可や在留資格申請、遺言書作成などの実務を個人で受託し、自由な裁量で仕事を進めることができます。
開業にかかる初期費用が比較的低いため、早期に事業をスタートできる点がメリットですが、一方で集客や営業、経理などの業務を一手に担う覚悟が必要です。
2. 行政書士法人や他士業事務所への勤務
行政書士法人や、税理士・司法書士法人に所属するスタイルもあります。この場合、会社員としての給与や福利厚生を受けながら、行政書士として実務経験を積むことが可能です。
安定した収入が得られ、先輩行政書士から実務を学べる環境も整っているため、スキルアップを図りたい人や独立前のステップとして活用したい人に適しています。ただし、求人数は限られており、収入の上限は独立開業より低くなる傾向があります。
3. 兼業型(サラリーマン行政書士)
一般企業に勤務しながら、個人として行政書士業務を行う「兼業行政書士」という働き方もあります。この場合、企業での就業規則に沿った副業許可が必要ですが、行政書士連合会への登録さえ済ませれば、自宅などで副業として活動可能です。
なお、企業の中で「企業内行政書士」として独占業務を行うことは法律上できませんが、法務部などで行政書士の知識を活かす働き方であれば問題はありません。
目指す収入に応じた働き方の選び方
行政書士としての年収は、選ぶ働き方や専門分野、実務経験の有無によって大きく異なります。そのため、まずは自分がどの程度の収入を目指したいのか、目標を明確にすることが大切です。
独立開業の場合:高収入だが不安定な面も
独立開業型の行政書士は、自身の努力と工夫次第で年収1,000万円以上を実現することも可能です。特に建設業許可や在留資格関連など、需要があり高単価な分野に特化することで、安定した高収益が期待できます。
ただし、開業当初は顧客獲得が難しく、収入は年間100万円〜300万円程度にとどまるケースも珍しくありません。事務所運営や集客活動、営業スキルの習得など、安定した経営基盤を築くまでには数年を要することが多いです。
勤務型の場合:安定性重視の働き方
一方、行政書士法人や他士業事務所などに雇用されて働く場合は、収入は比較的安定しています。たとえば、求人ボックス(2025年4月22日時点)によると、勤務行政書士の平均年収は約460万円、月給換算で38万円程度です。
また、伊藤塾による調査では、厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag(日本版O-NET)」において、行政書士の平均年収は551万4,000円とされています。
ただし、勤務型は昇給幅が限定的であることや、自分の裁量で仕事を選びにくいなどの面もあります。独立開業と比較すると、収入の上限はやや低くなる傾向にあります。
「企業内行政書士」として働く場合
企業に雇用され、法務や総務などの部署で法律知識を活かす働き方もあります。ただし、企業内で「行政書士」としての独占業務を行うことは、行政書士法により禁じられており、あくまで行政書士資格を持った会社員という扱いになります。
この場合、行政書士としての収入ではなく、会社員としての給与が主な収入源となります。企業によっては資格手当が支給されることもあります。
企業に勤務する行政書士のメリットとデメリット
行政書士として企業に勤務する場合、主に次の2つの形態があります。
- 行政書士法人などに雇用される「使用人行政書士」
- 一般企業で行政書士資格を活かす「企業内行政書士(※副業登録制)」
それぞれのメリットとデメリットを理解しておくことが、キャリア選択の判断材料となります。
使用人行政書士のメリットと課題
行政書士法人に雇用される使用人行政書士は、会社員と同様に固定給が支払われ、社会保険や福利厚生、退職金制度などの恩恵を受けることができます。先輩士業や他職種との連携を通じて、実務経験を積みながらスキルを高められる点も大きな魅力です。
また、比較的安定した環境の中で多様な案件に関われるため、行政書士としてのキャリアを築く初期段階には適した働き方ともいえるでしょう。
一方で、雇用形態にあるがゆえに、収入の上限はある程度固定される傾向があり、昇給も緩やかなケースが多いです。また、事務所の方針や方針転換に沿って業務を行う必要があるため、業務の自由度は独立開業に比べて低くなります。
一般企業における行政書士の活かし方
行政書士が一般企業で働く場合、「企業内行政書士」として登録し、その企業の業務に関わることは法律で認められていません。これは行政書士の業務が「独立・公正な立場で行うこと」を前提としているためです。
ただし、行政書士資格を持つ人が、企業の法務部門や経営企画部などで、その知識を活かして業務に取り組むことは問題ありません。また、企業に勤めながら、個人として行政書士登録をし、副業として独立業務を行う「サラリーマン行政書士」として活動することも可能です。
この場合、本業の就業規則で副業が許可されていることが前提となります。企業によっては、行政書士資格に対して資格手当を支給したり、昇進評価の対象としたりする例もあります。
独立開業する行政書士のメリットとリスク
行政書士として独立開業することは、多くの人にとって大きな目標であり、同時にリスクを伴う選択でもあります。ここでは、独立のメリットとデメリットを整理しておきましょう。
独立開業のメリット
最大のメリットは、自身の裁量で働き方や収入をコントロールできる点です。業務の内容、報酬の設定、働く時間や場所もすべて自由に決めることができ、理想のワークスタイルを実現しやすい環境です。
また、得意分野に特化して専門性を高めることで、競争力を高めることも可能です。たとえば、建設業許可や外国人関連の業務、相続・遺言関係など、需要が高く報酬単価も大きい分野に集中すれば、年収1,000万円以上を目指すことも現実的です。
さらに、行政書士には定年がなく、年齢を問わず長く活躍できる点も独立の魅力です。子育てや介護といったライフイベントとの両立もしやすく、自分のペースでキャリアを築いていけます。
独立開業のデメリットとリスク
一方で、独立開業にはいくつかの大きな課題もあります。なかでも、収入の不安定さは大きなリスクです。特に開業初年度は顧客がゼロからのスタートとなり、年収が100万円以下というケースも珍しくありません。
また、営業・経理・事務管理といった業務もすべて自分で行う必要があり、事業者としての総合的なスキルが求められます。時間の使い方、集客の工夫、競合との戦略的な差別化など、日々の経営判断が成功を左右します。
さらに、他の士業との競合も避けて通れません。弁護士・税理士・司法書士などは、行政書士と業務領域が重なる部分も多く、すでに顧問契約を結んでいる顧客に対しては、ワンストップで対応する士業のほうが選ばれる傾向にあります。
開業に必要な初期投資も一定の負担となります。行政書士会への登録料・入会金、事務用品やPC・プリンター、名刺・ホームページ制作費用などを含めると、総額で90万円〜150万円程度は見込んでおく必要があります。
行政書士試験に合格するための勉強法と時間管理
行政書士試験に合格するには、計画的かつ効率的な学習が欠かせません。特に初学者にとっては、法律という専門分野をゼロから学ぶ必要があり、正しい方法で取り組まなければ長時間をかけても結果が出にくくなります。
学習時間の目安とスケジューリング
一般的に、行政書士試験の合格に必要な学習時間は600時間〜1,000時間とされています。たとえば、800時間を目安とした場合、1日2.5時間の勉強で約10カ月、1日3時間で約9カ月の計算です。
このように長期にわたる学習が求められるため、「いつまでに何を終えるか」という学習スケジュールを立て、継続的に取り組むことが合格の鍵となります。
優先すべき科目と学習のポイント
行政書士試験では、行政法と民法が最も重要な科目であり、全体の得点に占める割合も高いため、まずこの2科目を重点的に学習しましょう。
憲法では判例の「判断枠組み」に注目しながら理解を深めることがポイントです。また、商法・会社法といった周辺科目もおろそかにせず、バランスよく学ぶ必要があります。
さらに、記述式問題も出題されるため、条文知識や理解力に加えて、文章構成力や論理的な説明力も養う必要があります。
効率的な学習方法と教材の選び方
独学の場合は、信頼できる基本テキストと六法、過去問、問題集を中心に学習を進めていくのが基本です。相性のよい教材を見つけ、自分のペースでコツコツ取り組むことが重要です。
一方で、効率的に合格を目指したい方や社会人で時間に制限がある方には、通信講座や予備校の活用も有効です。講義動画や模試、添削指導を活用することで、独学よりも学習効率が上がり、時間の節約にもつながります。
スキマ時間の活用とモチベーション維持
仕事や家庭と両立しながら学習する場合は、スキマ時間の活用が合否を分けるポイントになります。通勤中や昼休みなどに音声講義やアプリでの問題演習を行うなど、時間を“細切れ”に使って積み重ねることが有効です。
また、学習期間が長くなるからこそ、モチベーションの維持も非常に重要です。目標の明確化や、進捗管理アプリの活用、仲間との情報交換などを取り入れて、無理なく継続できる仕組みを整えましょう。
よくある疑問:行政書士って実際どうなの?
行政書士に関心を持つ方の中には、さまざまな疑問や不安を抱えている方も多いはずです。
「行政書士って本当に稼げるの?」「実務経験がないまま開業してやっていけるのか」「若くても通用するの?」「2人で開業するとメリットがあるの?」といった声はよく聞かれます。また、「行政書士の人気や将来性はどうなのか」といったテーマに関しても、明確な情報がないと不安になってしまうでしょう。
結論から言えば、行政書士という資格は、その活かし方次第で大きな可能性を秘めた国家資格です。独立志向がある方、専門性を高めて長期的なキャリアを築きたい方、法務系の副業を考えている方にとって、柔軟な働き方と高収益のチャンスを兼ね備えています。
一方で、開業直後は収入が不安定であったり、競合が多かったりと、現実的な課題も少なくありません。そうした課題を乗り越えるには、「資格取得後の学び直し」や「事業として成功させるスキル」が求められます。
だからこそ、行政書士という資格に可能性を感じている方は、情報収集だけでなく、早い段階で戦略的な準備を始めることが、将来的な安定と成長につながる第一歩となります。
🎓 行政書士や士業向けにキャリアの武器をつくるなら
財務コンサルタント養成講座・無料セミナーへ
行政書士としての強みをさらに高めたい方へ。
今後、企業経営者と深く関わるためには「財務」への理解が欠かせません。
当社では、士業・行政書士向けに実務で使える財務知識と提案力を学べる
【財務コンサルタント養成講座】を提供しています。
現在、無料セミナーも実施中。
「資格を活かして顧問契約を獲得したい」「収入を伸ばしたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご参加ください。
▶ 詳細・お申し込みはこちら
よくある疑問:行政書士って実際どうなの?
行政書士に関心を持つ方の中には、さまざまな疑問や不安を抱えている方も多いはずです。
「行政書士って本当に稼げるの?」「実務経験がないまま開業してやっていけるのか」「若くても通用するの?」「2人で開業するとメリットがあるの?」といった声はよく聞かれます。また、「行政書士の人気や将来性はどうなのか」といったテーマに関しても、明確な情報がないと不安になってしまうでしょう。
結論から言えば、行政書士という資格は、その活かし方次第で大きな可能性を秘めた国家資格です。独立志向がある方、専門性を高めて長期的なキャリアを築きたい方、法務系の副業を考えている方にとって、柔軟な働き方と高収益のチャンスを兼ね備えています。
一方で、開業直後は収入が不安定であったり、競合が多かったりと、現実的な課題も少なくありません。そうした課題を乗り越えるには、「資格取得後の学び直し」や「事業として成功させるスキル」が求められます。
だからこそ、行政書士という資格に可能性を感じている方は、情報収集だけでなく、早い段階で戦略的な準備を始めることが、将来的な安定と成長につながる第一歩となります。
🎓 行政書士や士業向けにキャリアの武器をつくるなら
財務コンサルタント養成講座・無料セミナーへ
行政書士としての強みをさらに高めたい方へ。
今後、企業経営者と深く関わるためには「財務」への理解が欠かせません。
当社では、士業・行政書士向けに実務で使える財務知識と提案力を学べる
【財務コンサルタント養成講座】を提供しています。
現在、無料セミナーも実施中。
「資格を活かして顧問契約を獲得したい」「収入を伸ばしたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご参加ください。
▶ 詳細・お申し込みはこちら
よくある疑問:行政書士って実際どうなの?
行政書士に関心を持つ方の中には、さまざまな疑問や不安を抱えている方も多いはずです。
「行政書士って本当に稼げるの?」「実務経験がないまま開業してやっていけるのか」「若くても通用するの?」「2人で開業するとメリットがあるの?」といった声はよく聞かれます。また、「行政書士の人気や将来性はどうなのか」といったテーマに関しても、明確な情報がないと不安になってしまうでしょう。
結論から言えば、行政書士という資格は、その活かし方次第で大きな可能性を秘めた国家資格です。独立志向がある方、専門性を高めて長期的なキャリアを築きたい方、法務系の副業を考えている方にとって、柔軟な働き方と高収益のチャンスを兼ね備えています。
一方で、開業直後は収入が不安定であったり、競合が多かったりと、現実的な課題も少なくありません。そうした課題を乗り越えるには、「資格取得後の学び直し」や「事業として成功させるスキル」が求められます。
だからこそ、行政書士という資格に可能性を感じている方は、情報収集だけでなく、早い段階で戦略的な準備を始めることが、将来的な安定と成長につながる第一歩となります。
🎓 行政書士や士業向けにキャリアの武器をつくるなら
財務コンサルタント養成講座・無料セミナーへ
行政書士としての強みをさらに高めたい方へ。
今後、企業経営者と深く関わるためには「財務」への理解が欠かせません。
当社では、士業・行政書士向けに実務で使える財務知識と提案力を学べる
【財務コンサルタント養成講座】を提供しています。
現在、無料セミナーも実施中。
「資格を活かして顧問契約を獲得したい」「収入を伸ばしたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご参加ください。
▶ 詳細・お申し込みはこちら
https://biz-recipe.jp/lp/financial-consultant-seminar-administrative-scrivener-05/