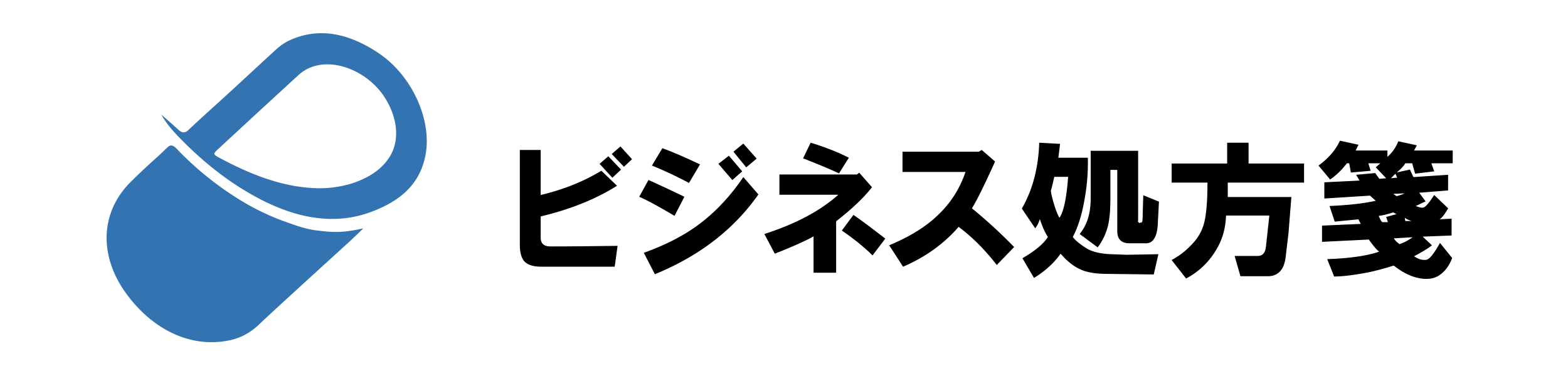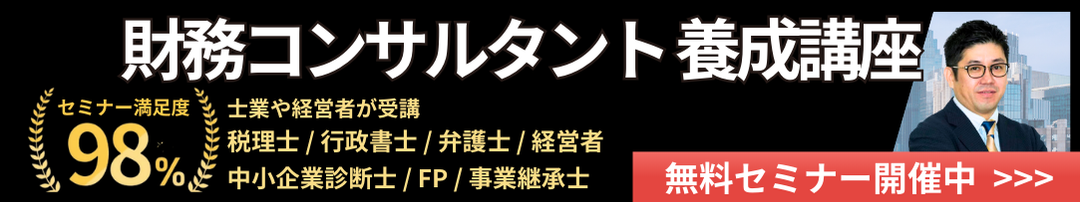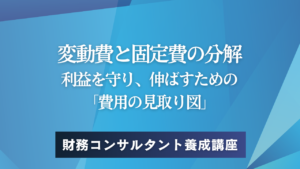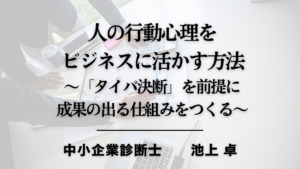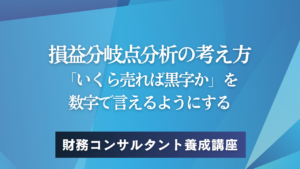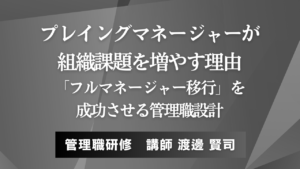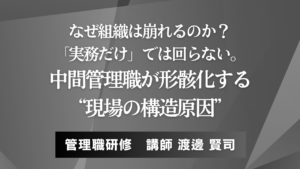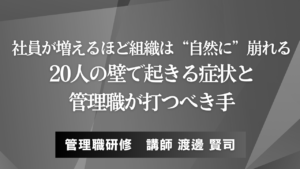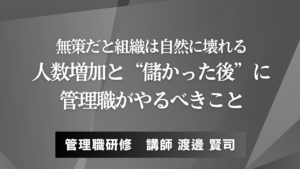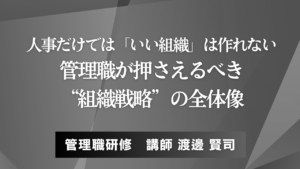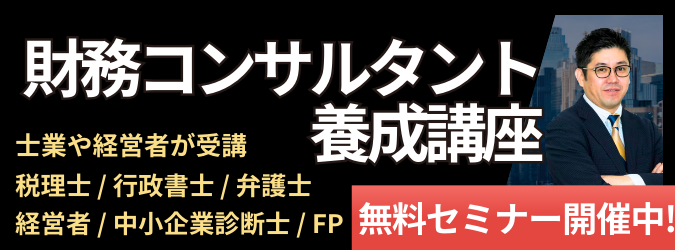行政書士の独占業務一覧 | 他士業との違いや業務範囲も解説
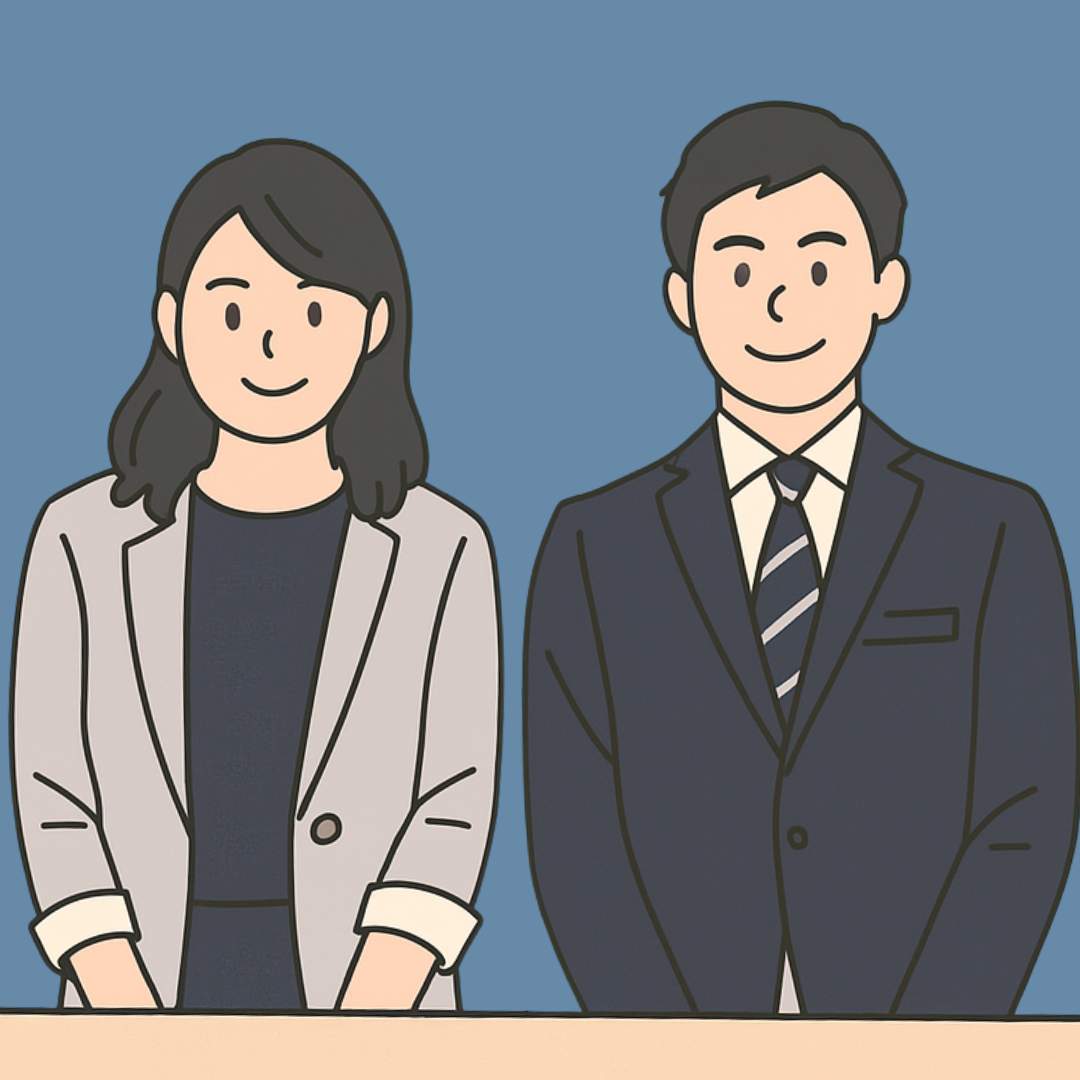
事務局
財務コンサルタント養成講座 運営事務局
2024年より講座を開講。これまでに税理士・行政書士・中小企業診断士をはじめ、保険募集人やIFAなど累計300名以上の専門家が受講。
財務支援/財務コンサルタントを目指す士業・コンサルタントの方に向けて、財務コンサルタントとしての実践ノウハウや働き方について情報発信を行っています。
行政書士は「街の法律家」とも呼ばれる国家資格であり、私たちの暮らしに密接に関わる法律実務の専門家です。主な業務は、官公署に提出する書類の作成や手続きの代理、権利義務や事実証明に関する書類の作成、そしてそれらに関する相談対応など、多岐にわたります。
なかでも、行政書士にしかできない「独占業務」は、法律により明確に定められており、高度な専門性を求められる領域です。
本記事では、行政書士の独占業務について詳しく解説しながら、他の士業との違いや業務範囲、さらには資格取得の方法やキャリアの展望についてもわかりやすく紹介していきます。
行政書士の独占業務とは?
行政書士の独占業務とは、法律に基づき行政書士以外の者が有償で行うことが禁止されている業務を指します。つまり、これらの業務は行政書士の資格を有する者だけが「業として」行うことが許される、独占的な業務領域です。
この制度は、国民の権利・義務や社会的な手続きに関わる書類を、一定の法的水準を満たす専門家が担うことで、制度の公正性や安全性を担保する目的があります。
次章では、具体的にどのような業務が独占業務として認められているのかを見ていきましょう。
行政書士の独占業務一覧
行政書士の独占業務には、以下の3つの柱があります。それぞれが行政書士法に明記されたものであり、他の資格者や一般の人が業として行うことは認められていません。
1. 官公署に提出する書類の作成
建設業許可や風俗営業許可、古物商許可、飲食店営業許可など、国や地方自治体の行政機関に提出する各種書類を作成します。これらは、許認可や届出、報告書など多岐にわたり、正確な法的知識が求められます。
2. 書類提出の代理
上記のように作成した書類を、依頼者に代わって官公署へ提出する業務です。単なる「郵送代行」とは異なり、申請全体のプロセス管理や事前相談への対応も含まれます。
3. 書類作成に関する相談対応
どのような書類を、どのタイミングで、どのように作成すべきかといった実務的なアドバイスも、行政書士にしかできない業務の一つです。法律に則った正しい手続きの案内が求められます。
独占業務の具体例と対応分野
行政書士が扱う申請業務は、数百種類に及ぶとも言われ、その業務範囲は非常に広いのが特徴です。代表的な申請手続きには、以下のようなものがあります。
- 建設業許可申請
- 風俗営業許可申請
- 古物商許可申請(警察署へ)
- 飲食店営業許可申請(保健所へ)
- 農地転用許可申請
- 旅館業営業許可申請
- 車庫証明・自動車登録関係書類の作成
- 入管業務(在留資格・ビザ申請の取次)※入管取次資格者に限る
これらは、申請者本人でも手続き可能ですが、法令知識や実務経験が必要なため、行政書士のサポートが重宝されています。
他士業との違いと業務の線引き
行政書士と他の「士業」には、それぞれ専門とする分野があり、業務範囲が重なることもありますが、法的に明確な区分があります。
| 士業 | 独占業務内容 | 行政書士との違い |
|---|---|---|
| 弁護士 | 訴訟代理、法律相談、紛争解決 | 紛争に関わる業務や訴訟代理は行政書士には不可 |
| 司法書士 | 登記申請の代理、不動産・法人登記 | 登記関連業務は司法書士の独占業務 |
| 社会保険労務士 | 労働・社会保険の手続代理、就業規則の作成など | 行政書士も一部対応可能な書類はあるが範囲は限定 |
| 税理士 | 税務申告、帳簿作成、税務相談 | 行政書士は税務書類作成や申告業務は行えない |
行政書士は、主に「予防法務」に関わる書類の作成や相談を担う立場にあります。対立・紛争を含む案件や強制力を伴う手続きについては、それぞれの専門士業に委ねられます。
独占業務に限らない、行政書士の活躍の場
行政書士は、独占業務に加えて、資格者でなくても行える「自由業務」にも多数対応しています。主な例としては、次のような業務があります。
- 契約書や内容証明郵便の作成
- 遺産分割協議書の作成(※紛争を含まない場合)
- 法人設立時の書類作成(定款、議事録など)
- ドローン飛行許可、著作権登録などの専門申請
これらは、法律知識を前提とした高品質な書類作成を求められる場面で、行政書士の専門性が強みとなります。
行政書士の資格要件
行政書士として活動するには、まず資格を取得し、行政書士会に登録する必要があります。行政書士資格を取得する最も一般的な方法は「行政書士試験への合格」ですが、他にもいくつかの取得ルートが存在します。
年齢・学歴の制限なし
行政書士試験には、年齢や学歴、国籍などの制限が一切ありません。中卒・高卒の方でも受験でき、実際に10代から80代までの幅広い年齢層が挑戦しています。ただし、行政書士として登録し業務を開始できるのは「20歳以上」と定められているため、未成年で合格した場合は成人するまで登録を待つ必要があります。
この開かれた受験制度により、社会人のキャリアチェンジや定年後の再チャレンジなど、多様な層に門戸が開かれています。
行政書士になる3つの方法
行政書士資格は、試験合格に限らず、以下の3つのルートで取得可能です。
1. 行政書士試験に合格する
最も一般的な方法です。試験は年1回、例年11月に実施され、合格発表は翌年1月下旬。出題は「行政書士の業務に必要な法令等」と「一般知識」に大別され、記述式と択一式の両方が含まれます。
合格率は毎年10〜13%前後と決して高くはありませんが、計画的な学習で合計点数の6割以上を取ることができれば合格が可能です。合格後は、必要書類を提出して行政書士会に登録し、正式に業務を開始できます。
2. 公務員としての実務経験を活かす(特認制度)
一定年数以上の行政職経験がある国家公務員・地方公務員は、試験を経ずに行政書士資格を取得できる「特認制度」があります。
- 国家公務員:行政に関する事務を17年以上
- 地方公務員:同様の業務を20年以上
こうした経験がある場合、行政書士会への申請により、資格取得が認められます。長年の行政実務を民間でも活かせる制度です。
3. 他の士業資格を活用する
弁護士・弁理士・公認会計士・税理士のいずれかの資格を持つ方は、行政書士試験を免除され、登録により行政書士として活動できます。
また、行政書士の資格を取得しておけば、社会保険労務士など他資格へのステップアップにも役立つ場面があります。
行政書士試験の難易度と学習のポイント
行政書士試験は、法律知識のない初心者にとっては難易度が高く感じられるかもしれません。出題範囲は広く、合格率は約10〜13%とやや低めです。
他資格との比較
- 司法書士・予備試験(弁護士)に比べれば合格率は高い
- 宅建(宅地建物取引士)に比べるとやや難易度が高め
初学者が独学で合格することも可能ですが、法律用語や文脈に慣れるまでは苦労する方も多いため、市販の教材だけでなく通信講座や専門スクールを活用するのも有効です。
行政書士としての就職・働き方
行政書士の資格を取得すると、多様な働き方の選択肢が広がります。事務所勤務、企業法務部への就職、さらには独立開業まで、キャリアの方向性は人それぞれです。
行政書士の年収事情
行政書士の年収は、働き方によって大きく異なります。
企業勤務や事務所勤務の場合
行政書士事務所や法律系事務所に就職した場合、年収はおおむね200万円〜600万円程度。初年度は250万円前後が目安で、経験を重ねることで徐々に年収が上がる傾向があります。
独立開業の場合
独立した行政書士の平均年収は約600万円とされています。ただし、得意分野や営業力によって年収は大きく異なり、1,000万円を超える方も少なくありません。建設業許可や在留資格申請など、専門性の高い業務は高単価となる傾向があり、収入アップを狙うには注力分野の選定が重要です。
一方、開業初期は顧客獲得が難しく、年収が低くなることもあるため、軌道に乗るまでの戦略が求められます。
行政書士資格を活かせる求人
行政書士の資格は国家資格であり、法律文書の作成スキルを活かせる場面が多く存在します。主な就職先には、以下のようなものがあります。
- 行政書士事務所、弁護士事務所、司法書士事務所などの士業系事務所
- 一般企業の法務部・総務部
- 外国人の在留管理や国際法務を扱う専門部署
これらの求人では、行政書士資格の有無が採用に大きく影響する場合もあり、未経験者を対象とした「補助者」採用から経験を積めるケースもあります。
独立開業の魅力と課題
行政書士の大きな魅力の一つが、試験合格後すぐに独立開業できる点です。実務経験が必須ではないため、若年層でもキャリアの早い段階から開業が可能です。
独立のメリット
- 仕事の選択や働き方の自由度が高い
- 定年がなく、長く現役として働ける
- 個人の努力次第で高収入も可能
開業に必要な準備
- 行政書士会への登録費用
- 事務所の開設・設備投資
- 顧客獲得のための営業活動
- 会計処理や経営知識の習得
「士業=専門職」ではありますが、実際には自営業者としての経営感覚も不可欠です。顧客ニーズを読み取り、専門性を武器に営業戦略を立てていく力が求められます。
行政書士を目指すうえでの注意点
行政書士は魅力的な国家資格であり、キャリア構築にも役立ちますが、資格取得後の実務や継続的な学習も重要です。
登録年齢の制限に注意
行政書士試験は年齢に関係なく受験できますが、登録には20歳以上という制限があります。10代で合格した場合でも、登録・開業は成人後となるため、進路設計の際には留意が必要です。
継続的な学習と専門分野の確立
法律や制度は日々変化するため、行政書士として活躍し続けるには、継続的なインプットが不可欠です。特に独立を目指す場合、下記のような準備が重要です。
- 最新の法改正情報の習得
- 得意分野・専門分野の確立
- 実務スキルの向上(相談対応・書類作成力)
- 同業者とのネットワーク形成
特定分野に強みを持つことで、他の行政書士との差別化が図れ、安定した集客にもつながります。
行政書士としてのキャリアや独立を本気で目指すなら、実務力のある財務知識も武器になります。
「財務コンサルタント養成講座」では、士業やコンサルタント向けに、顧客から信頼される財務スキルの習得を支援しています。
▶ 無料セミナーへのご参加はこちら
https://biz-recipe.jp/lp/financial-consultant-seminar-administrative-scrivener/