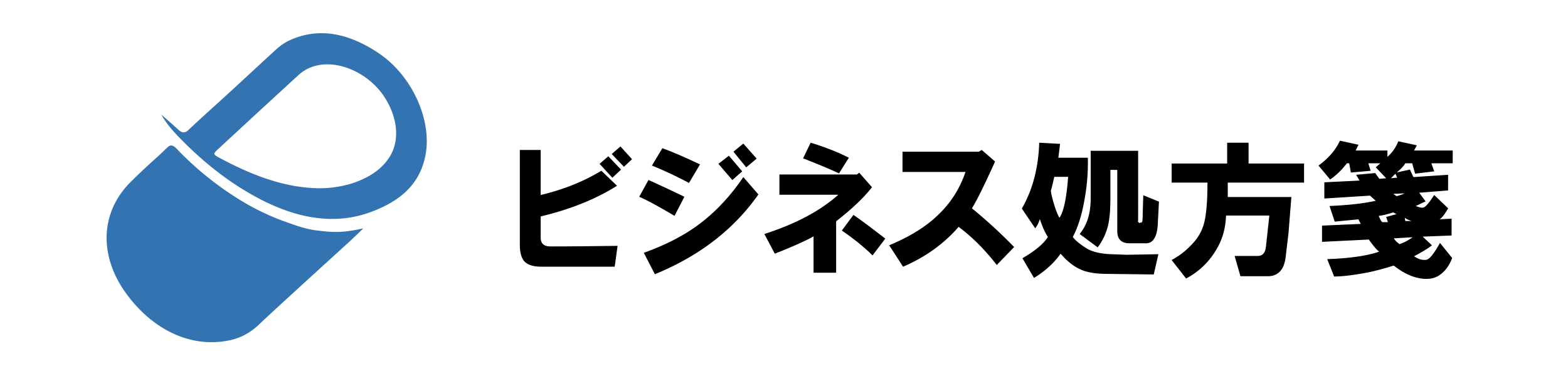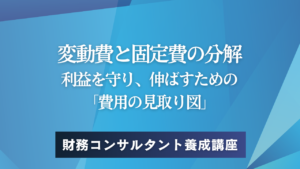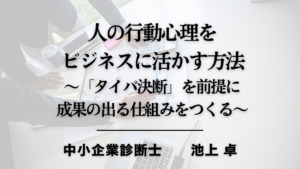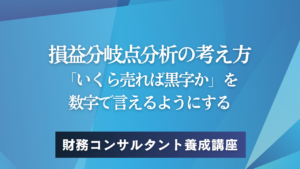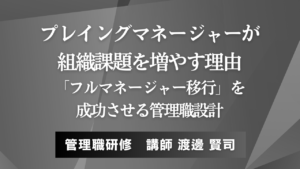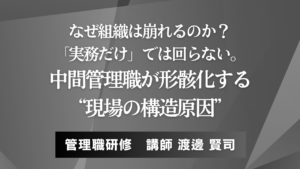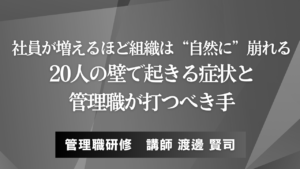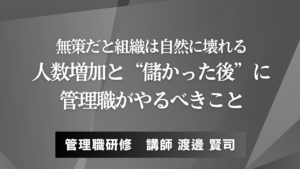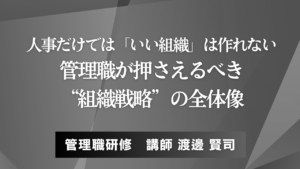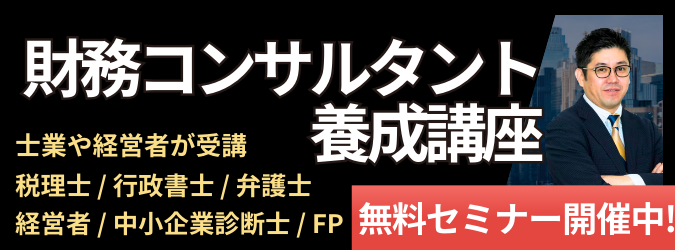中小企業が異文化人材を活かすには (ベトナム人材との共創)

池谷 卓
中小企業診断士
約30年以上にわたり、素材メーカーに勤務し、国内外の生産設備・ライン
設計・保全や生産拠点運営、新事業開拓、経営企画、DX推進等を経験。2023年に中小企業診断士として登録。
はじめに
いまや大企業だけでなく、多くの中小企業でも外国人が戦力として活躍しています。2024年10月末時点において日本で働く外国人は約230万人、そのうち約4分の1にあたる約57万人がベトナム人です。
ベトナム人労働者の在留資格を見ると、技能実習生が約22万人、そしてエンジニアや技術者など、専門的・技術的分野で働く人が約20万人にのぼります。特に後者の方々は、すでに中堅・中小企業の現場でも、設計・開発・生産管理などの中核業務を担っており、不可欠な存在となりつつあります。ベトナムからの人材流入が増えている背景には、円安下でも相対的に高い日本の賃金、日本文化への親しみ、そして社会保障を含めた生活環境の安定といった要因があるとされています。
現時点では、こうしたベトナム人材を「労働力」として捉えている中小企業が多いかもしれません。しかし、これからの時代においては、彼らを将来の経営を担うパートナーとして育成・活用する視点がより重要になってくるでしょう。本稿では、そうした観点から、ベトナム人材を受け入れるうえで中小企業が理解しておくべき文化的な特徴や価値観、コミュニケーションのポイントなど、実務に役立つ知見をご紹介していきます。
ベトナムの方々の価値観や考え方
家族ファースト
ベトナムの人々は「家族を大切にする」とよく言われます。ただし、その意味合いは私たち日本人の感覚とは少し異なります。日本では、「家族を大切にする」とは自分が家族を思いやり、信頼し、共に過ごすことを指します(主体は“自分”)。一方、ベトナムでは、意思決定の中心に“家族”そのものがあるという考え方です。自分の進路や仕事の選択でさえも、家族の意向や期待を優先することが一般的です。
つまり、個人の評価は“自分一人”ではなく、“家族という集団の中での役割”によって決まるという文化的価値観があります。
階層主義
ベトナムでも、年齢や役職に基づいた上下関係を重んじる傾向があります。目上の人に敬意を払い、指示に従うことが自然と求められます。この傾向は、ベトナム語の中にある年齢や立場ごとに異なる呼称にも表れています。こうした文化的背景により、組織の中での自分の立ち位置や責任は、周囲の評価や承認によって明確になるという特徴があります。
チームワーク
ベトナムの方々もチームワークを重視します。ただし、日本のような「空気を読む」文化とは少し異なり、信頼関係に基づいた明確な関係性がある場合にチームワークが発揮されるという点が特徴です。
儒教的価値観の影響もあり、個人より集団の調和を重視する傾向があります。一方で、都市部の若者層には、個人主義的な考え方が浸透し始めており、形だけのチームワークが生まれるケースも増えています。
説得スタイル
説得のスタイルには、大きく「原理原則から説明するタイプ」と「実例・経験から話すタイプ」があります。ベトナムの方々は、日本人同様に、具体的な経験や実例から話を進める傾向(応用優先型)が強いようです。そのため、背景にある理論や本質的な原因を掘り下げるより、目の前の事象に対して対処的に対応する場面が多くなることがあります。マネジメントの場では、この傾向を理解しておくと誤解を避けられます。
理解と反応
ベトナムの方々は、特に目上の人に対して「わかりました」と返事をする傾向がありますが、それが本当に理解していることを意味しているとは限りません。これは、「わからない」と言うことで自分の評価が下がることを避けたり、相手の顔を立てようとする文化的配慮が背景にあります。したがって、指示や説明をした際は、内容を確認しながら丁寧にフォローすることが重要です。
時間感覚
日本人のような「時間厳守」の文化とは異なり、ベトナムの方々は比較的時間に対して柔軟です。
たとえば、「会議の5分前に準備して席に着く」ことが当然という感覚は、ベトナムではあまり共有されていません。とはいえ、契約や法律上のしめきりなどにはしっかり対応しますので、場面によって求める行動を明確に伝える必要があります。
※さらに深く理解したい方には、エリン・メイヤーの『カルチャーマップ』を活用することをおすすめします。文化を8つの軸で捉え、実践的な比較が可能です。
「ちがい」を力に変えるためには
ベトナムの方々の価値観には、日本人と似ている部分もあれば、大きく異なる点もあります。これらは文化や社会的背景に根ざした特徴ですが、あくまで一般的な傾向です。すべてのベトナム人がそう考えていると決めつけること(ステレオタイプ)は避けるべきです。
重要なのは、自分たち日本人の文化や考え方を見つめ直し、それと比較しながら、目の前の個々人の特性を尊重し対応することです。特に意識したいのはコミュニケーションです。あいまいな表現や察してもらう前提ではなく、「はっきり、丁寧に伝えること」、そして相手が安心して本音を話せる関係づくりが欠かせません。
こうした取り組みを積み重ねることで、社内に新たな風土や文化が生まれ、日本とベトナムの架け橋となる「コネクター人材」が育っていきます。彼らはやがて、会社の将来を担う存在となるでしょう。
まとめ
異文化理解は、日本人にとって簡単なことではありません。特に、外国人との接点が少ない地域や企業にとっては、戸惑いや誤解が生まれやすいのも事実です。しかし見方を変えれば、自国文化を深く理解しているからこそ、他文化との違いにも気づきやすく、学びに転換しやすいとも言えます。
今後、日本の中小企業が持続的に成長していくためには、外国人を「労働力」としてだけでなく、「将来の経営を支える仲間」として迎える視点が欠かせません。そのためには、異文化理解を経営課題のひとつとして正面から向き合うことが重要です。
本稿が、皆さまの職場や組織づくりのヒントになれば幸いです。
なお、今回ご紹介した内容は、
- ベトナムでIT企業を経営していた経験者
- EPA制度による看護・介護職の教育担当者
へのヒアリングをもとにまとめたものです。
当社3Rマネジメントでは、外国人材のマネジメントや育成支援に関する豊富な実績があります。
異文化人材に関するお悩みや課題がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。