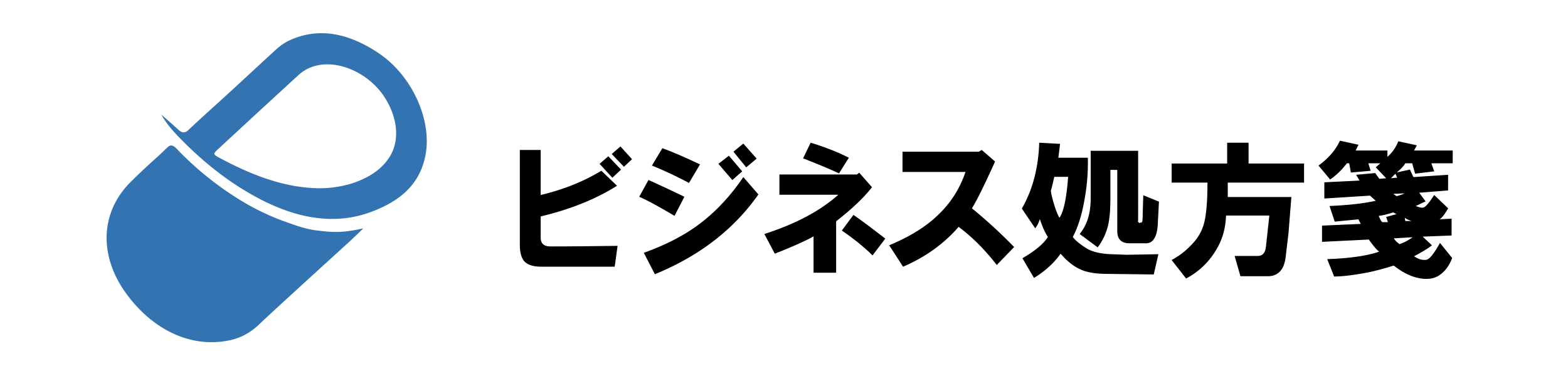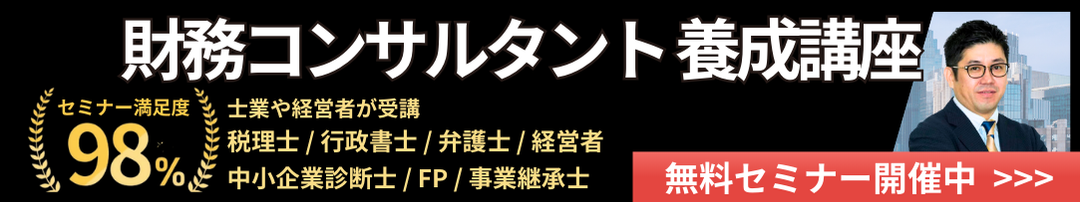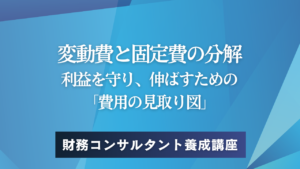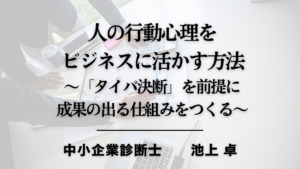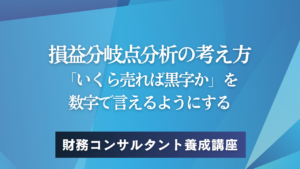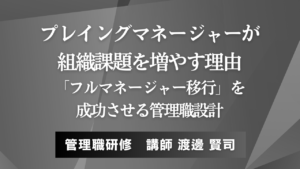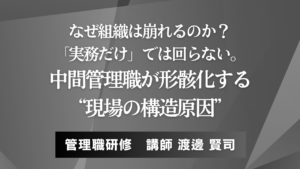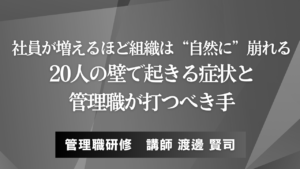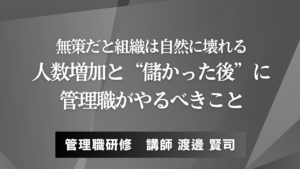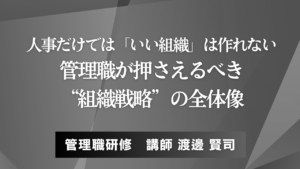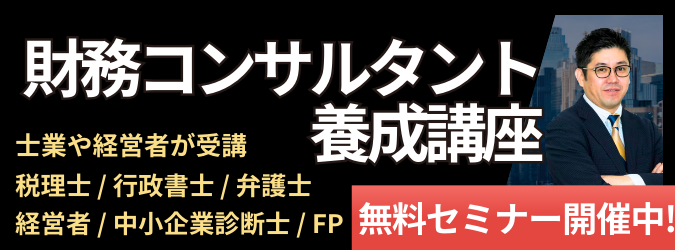役員退職金(役員退職慰労金)とは?メリットやデメリットをわかりやすく解説!

猪俣 友樹
中小企業診断士/
E資格
中小企業診断士/JDLA Deep Learning for Engineer(E資格)
ノンバンクでAI、データ分析を活用したマーケティング、リスク管理業務に従事。
データを駆使した課題解決や与信モデルの構築・運用を経験。
役員退職金は、長年の会社への貢献に対する報酬として位置づけられています。本記事では、中小企業における役員退職金の意義、メリット、デメリット、そして最新の動向について解説します。
役員退職金(役員退職慰労金)とは?
役員退職金(役員退職慰労金)は、取締役や監査役などの役員が退職する際に支給される退職金のことです。一般的に、役員が在任中の功績や貢献に対する報酬の一部として位置づけられています。役員退職金は以下の要件を満たす必要があります。
- 退職した役員に対して支給されるものであること
- 退職を事由として支給されるものであること
- 支給額が退職した役員の退職の事情に照らして相当であること
支給の決定は通常、株主総会の決議または定款の規定に基づいて行われます。役員退職金は、会社の定款や株主総会の決議によって決定されますが、具体的な金額や支給方法については、取締役会などで決定されることが一般的です。これは、適正な基準を設けることで、税務上のリスクを軽減しつつ、経営者への報酬として機能することを意味します。
役員退職金の支給には、会社の規模や業績、役員の在任期間、貢献度などが考慮されます。中小企業においては、オーナー経営者の引退に伴う事業承継の際に重要な役割を果たすこともあります。
役員退職金の計算方法
役員退職金の計算方法を2パターン紹介します。
功績倍率法
最も一般的な計算方法は「功績倍率法」です。
計算式は以下の通りです。
役員退職金 = 退職時の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
例えば、退職時の月額報酬が80万円で勤続年数が20年、功績倍率が3倍であれば、役員退職金は以下のように計算されます。
4,800万円 = 80万円 × 20年 × 3
1年当たり平均額法
1年当たり平均額法は、功績倍率法を補完する方法として、特定の状況下で使用されます。
功績倍率法は、役員の最終報酬月額が適正でない場合や、功績倍率法を採用すると役員退職給与の適正額が著しく低額となってしまう場合に用いられます。
計算式は以下の通りです。
役員退職給与の適正額 = 類似法人の退職給与の1年当たりの平均額 × 在任年数
1年当たり平均額法は、功績倍率を用いた方法によることが不合理であると認められる特段の事情がある場合に使用されます。同業種・同規模法人の役員退職金の支給データを収集し、1年当たりの平均額を算出する必要がありますが、非公開会社の退職金支給状況を収集するのは困難な場合があるため、顧問税理士等を通じて統計データを入手するなどの対応が必要です。
通常、会社の役員退職金規程では原則として功績倍率方式に基づいて支給額を定め、特段の事情があった場合の計算上のオプションとして1年当たり平均額法を採用することが推奨されます。また、課税庁が訴訟等の場面で「不相当に高額な金額」を算定する際に、功績倍率方式を補完する方法として1年当たり平均額法が採用されることもあります。
結論として、役員退職金の算定には主に功績倍率法が用いられますが、特殊な状況下では1年当たり平均額法が適用される可能性があります。いずれの方法を採用する場合も、税務上のリスクを最小限に抑えるため、専門家に相談することが重要です。
社員の退職金との違い
社員の退職金は長年の勤務に対する感謝や報償であり、 高度成長期には、現在支払いきれない賃金を後で退職金として支払うという意味合いがありました。役員退職金と社員の退職金にはいくつかの違いがありますので、以下に整理します。
| 項目 | 社員の退職金 | 役員退職金 |
| 規定の有無 | 通常、就業規則や退職金規程に基づいて支給 | 定款または退職金規程で定めることが一般的だが、必須ではない。 |
| 決定プロセス | 会社が定めた基準に従って自動的に計算されることが多い | ●定款に規定がある場合 株主総会決議不要 (株主総会での決議も可) ●退職金規程がある場合 株主総会決議 (取締役会への一任可) ●定款・規程がない場合 株主総会決議が必要 |
| 計算方法 | 一般的に勤続年数と最終給与に基づく | 功績倍率法や1年当たり平均額法など |
| 税務上の取り扱い | 損金の額に算入可。ただし例外あり。※ | 適正な金額であれば全額損金算入可能 |
※特殊関係使用人(役員の親族や婚姻関係の近い者、役員から生計の支援を受けている者など)に対する退職金のうち、過大な部分については損金算入できません。
役員退職金の決定方法は、会社の状況(定款の規定の有無、退職金規程の有無)によって異なります。具体的な金額や支給方法は、多くの場合、取締役会に一任されますが、その際も一定の基準に基づく必要があります。税務上の取り扱いについて、役員退職金は「適正な金額」であることが重要です。不相当に高額な場合、税務署から指摘が入り、損金算入が認められない可能性があります。
社員の退職金と役員退職金は、その性質や決定プロセスが異なるため、企業は両者を明確に区別して管理する必要があります。
役員退職金(役員退職慰労金)のメリット
役員退職金には会社と退任役員の双方にとって、いくつかのメリットがあります。
- 節税効果
役員退職金は、適正な金額であれば全額が損金(経費)として認められ、法人税等の節税効果が得られます。課税所得を圧縮し、法人税等の負担を軽減できます。
法人税の基本的な計算式は以下の通りです。
法人税額 = 課税所得 × 法人税率 – 税額控除
ここで、課税所得は次のように計算されます。
課税所得 = 益金(収入) – 損金(経費)
役員退職金を支給することで、損金(経費)が増加し、結果として課税所得が減少し、法人税額が軽減されます。 - 自社株式の評価引き下げ
役員退職金の支給は会社の純資産を減少させるため、自社株式の評価額を引き下げる効果があります。これは、事業承継時の株式譲渡や相続における税負担を軽減するのに役立ちます。 - 人材確保とモチベーション向上
将来の退職金支給を約束することで、優秀な人材を役員として長期的に確保しやすくなります。また、現役の役員のモチベーションを高める効果も期待できます。 - 社会保険料の負担軽減
役員退職金は社会保険料の算定対象外となるため、会社側の社会保険料負担を抑えることができます。
役員退職金(役員退職慰労金)のデメリット
役員退職金には多くのメリットがある一方で、いくつかの注意すべき点やデメリットも存在します。
- 資金流出
役員退職金の支給は、会社にとって大きな資金流出を意味します。特に中小企業では、まとまった金額の支出が財務状況に大きな影響を与える可能性があります。 - 株主総会での承認の必要性
役員退職金の支給には通常、株主総会での承認が必要です。この過程で株主間の意見の相違や対立が生じる等、会社の内部統制に影響を与える可能性があります。 - 税務調査のリスク
役員退職金が「不相当に高額」と判断された場合、税務調査の対象となり、損金算入が認められない可能性があります。これは追徴課税のリスクを意味し、会社の財務に影響を与える可能性があります。 - 会計処理の複雑化
役員退職金引当金を計上する場合、税効果会計の適用が必要となり、会計処理が複雑化する可能性があります。
役員退職金(役員退職慰労金)のまとめ
中小企業の事業承継において、役員退職金は依然として重要な役割を果たしていますが、過度に高額な退職金は税務上のリスクを伴うため、慎重な対応が求められています。
事業承継や人材確保の観点から、自社の状況に応じた適切な役員退職金制度を検討することが重要です。
財務コンサルタント養成講座で財務の知識を深め、役員退職金の最適な活用を学ぶ方法とは?
役員退職金についてポイントをご理解いただけたでしょうか。
これを機に、さらに高度な財務知識を身につけてみませんか?
財務担当者や税理士といった士業の方に向けた「財務コンサルタント養成講座」では、プロフェッショナルとしての財務スキルを一層強化できます。実践的な財務戦略を身につけることで、自社やクライアント企業の成長を後押しし、さらなる信頼を得られるでしょう。
今こそ、専門家としての知識を深化させ差別化を図るチャンスです。
無料セミナーに参加し、第一歩を踏み出しましょう!