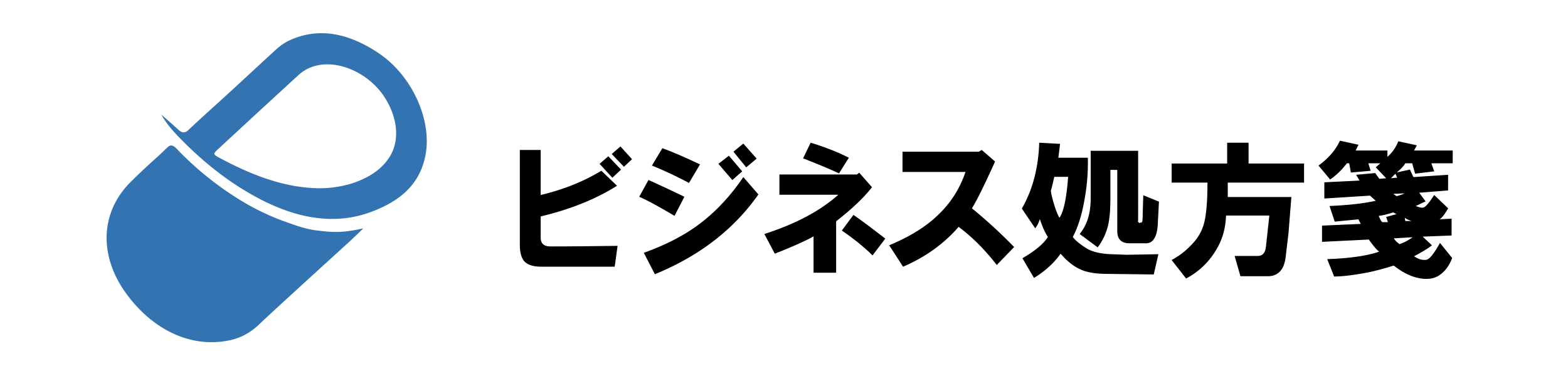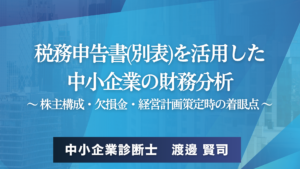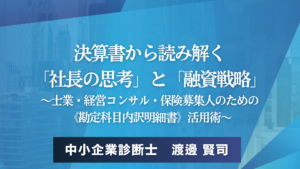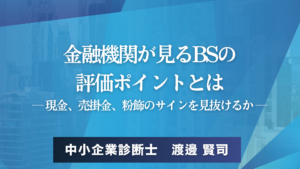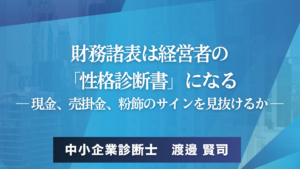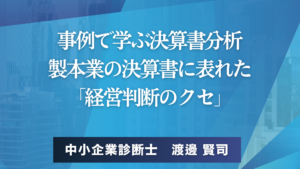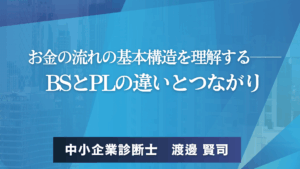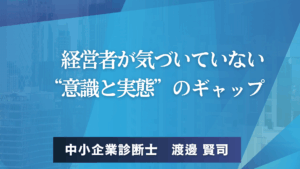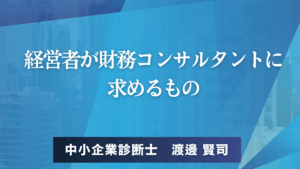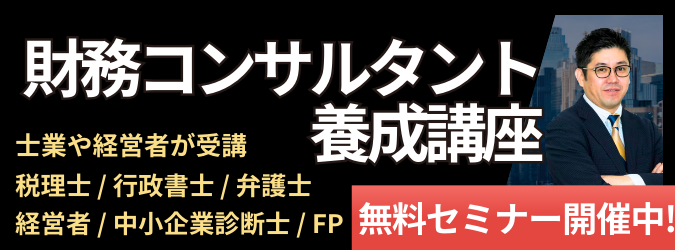孤立した事業承継者~「引き継ぐ覚悟」のない組織が迎える、未来なき結末~

池谷 卓
中小企業診断士
約30年以上にわたり、素材メーカーに勤務し、国内外の生産設備・ライン
設計・保全や生産拠点運営、新事業開拓、経営企画、DX推進等を経験。2023年に中小企業診断士として登録。
後継者不足だけではない、事業承継の本当の問題とは?
ご存じの通り、日本の中小企業が抱える深刻な経営課題の一つに「事業承継」があります。近年では、黒字企業が、後継者選びや承継準備に失敗して、やむなく廃業を選ぶ例も少なくありません。その結果、多くの人々が働く場所を失い、地域経済の基盤が崩れていく――そんな危機的状況が、現実のものとなりつつあります。
このような後継者不在の実態は、経済産業省『中小企業白書2025年版』**にも明確に表れています。たとえば、80歳代の経営者においては、実に36.5%が「後継者がいない」(あるいは「後継候補の承諾が得られていない」)と回答しており、憂慮すべき状況であると言えます。
では、「後継者さえ見つかれば解決なのか」というと、決してそうではありません。
今回ご紹介する事例の主人公、吉田 修さんは、それについてこう語っています。
「財務・税務・法務の整理? 取引先との信頼?もちろん大切だが、それらは時間をかければ、ある程度は何とかなるよ。事業承継の本質は、鍛冶屋の“火床”を引き継ぐようなことなんだ。」
彼の言葉は続きます。
「中小企業は、経営者個人の判断と人間関係に強く依存している。だからこそ、社長が変われば、
組織が止まってしまう──そんなことも、珍しくないんだ。大企業のように中間管理職が組織を支える構造がないため、いくら承継者が優秀でも、“生き抜きたいと思う人”がそこにいなければ、事業承継は難しいよ。」
ある承継者の苦い経験
突然の打診、静かな情熱
「修、お前、うちの会社を継いでみないか──」
大手インフラ会社で長年IT業務に携わってきた修氏は、定年まで数年という頃、伯父にあたる会長からそう声をかけられた。
母方の長男である80歳後半の伯父は、会長として自動車部品を製造する会社を、社長の弟と経営している。
製造業、しかも異なるジャンルの製品を手がけるその世界は、修氏にとって全くの畑違いだった。
しかし、“経営”という未経験の分野に対して、修氏は今までの経験を生かし、あえて飛び込むことを選んだ。
そこには、血縁を超えて自分を頼ってくれる伯父の想い、そして「第二の人生は誰かの役に立ちたい」という、自身でも驚くほど強い思いがあった。
不安と戸惑いが交錯する中、最後に彼の背中を押したのは──勇気、そしてその思いだった。
希望、学び、そして一歩ずつ
覚悟していたとは言え、今まで経験してきたITの世界と製造の違いに、入社当初は戸惑った。しかし、元来負けず嫌いの修は、社内外の全てを学ぼうと、製造現場や経理、営業業務の理解、仕入れ先や顧客の理解と関係性構築など、まるで新入社員のように取り組んでいた。
誰もいない部屋で、明日の経営会議資料をまとめていた時に、ふいに会長に声をかけられた。
「修、事業計画書って前の会社で作ったことあるか?」と言うと続けて、
「おれは、お前にこの会社の事業計画書を策定してもらいたいと思っている。そこで、社長と一緒に中小企業診断士と取り組んでくれないか?」と言われた。
修は一瞬迷いながらも、「会社の未来を描いて、もっと良い会社にしなくては」との使命感とやりがいを感じた。
動かない組織、響かない言葉
半年後、修は全社員に向けて会社の現状やそこから目指すべき姿と実現手段を描いた事業計画を説明会で語っていた。しかし、社員の反応は薄いというより、他人事だった。一緒に計画を策定した社長も、無関心に修を支えることはなかった。
その日の夜、事務所には、執行役員で製造部長の佐藤と修だけが残っていた。
コーヒーを口に運びながら、佐藤がぽつりとつぶやいた。
「うちの社員のほとんどは、私も含め給料さえもらえればそれでいい、と思っていますよ。」
静かに、しかし重たく落ちた言葉だった。
「意見が取り入れられたこともない。成果を出しても、何も変わらない。そんな日々を数十年も過ごせば……誰だって諦めますよ。」
そして、「今さら事業計画だなんて言われても……正直、誰も本気にはしませんよ、経営企画部長なら、わかりますよね。」と続けた。
修は返す言葉を探したが、見つけられなかった。
翌日、修は「大半の社員が、事業計画書に賛同してくれない」事を、藁をもすがる思いで中小企業診断士に相談してみた。すると診断士の口からは、
「それは、あなたの言葉が、社員の心を動かすには不十分だったということかもしれませんね。」
と思いもしない、無機質な言葉が返ってきた。
修は診断士と初めて会った時の彼女の言葉を、思い出した。
「私は伴走者としてサポートさせていただきます。あくまでも主役は、お客様です。」
そして、彼女の伴走とは、「能動性や共感性」を伴わない「ただ一緒にいる」意味だったと気が付いた。
この事業承継は、“そもそもの土台もなければ、支援する環境もなかったのかもしれない”と、修は思った。
退職、そして残されたもの
それから半年が過ぎた年末近いある日、工場からの帰り道。夕日の入り込む車の中で、ふと修は思った。
「俺は何をしているのか、こんなことに、残りの人生を費やしていいのか…?」
翌朝、修は会長に封筒を手渡した。
あれから数年経つが、修氏の耳に入ってくるのは、何も変わらず年老いた会長と社長が二人三脚で会社を回しているという話である。あれほど手間をかけた事業計画も、結局誰にも実行されることはなかった。
近頃、修は”あの会社には、承継の前に燃えようとする火がなかった。”
しかし、”自分は残っているはずの火種を探すことも、火を起こす手立ても、持ち合わせなかった”
と、思い始めている。
後継者の孤立を生まないために——組織が変わる覚悟を持てるか
今回のお話のように、事業承継は後継者の資質や努力だけでは、決して成り立ちません。
必要なのは、現経営者による“引き継ぐ覚悟”と“育てる責任”。 そして、承継者が孤立しないよう、組織全体を巻き込む設計と支援です。
当社3Rマネジメントの中小企業診断士は、計画書の作成だけで終わりません。 承継者と現経営者の間に立ち、組織の状況を理解し、現場の声を拾い、 “人が共感して・それぞれの役目で動く”ための仕掛けを共につくります。
3Rマネジメントの診断士が目を向けているのは、人と組織そのものです。 事業を動かすのは、資産ではなく“人”。 どれほど優れた技術や商品、ブランドがあっても、それを動かす“意思”と“人”がいなければ、会社はただの器に過ぎません。
「継がれる会社」を、能動性と共感性を持った伴走支援で育てる──それが、私たちの使命です。
「この会社を、次につなぎたい。」
そう思ったとき、あなたの隣に、話を聞いてくれる誰かはいますか?
3Rマネジメントは、そんな伴走者でありたいと考えています。
事業承継の無料相談も実施しております。
ぜひ一度こちらからお問い合わせください。