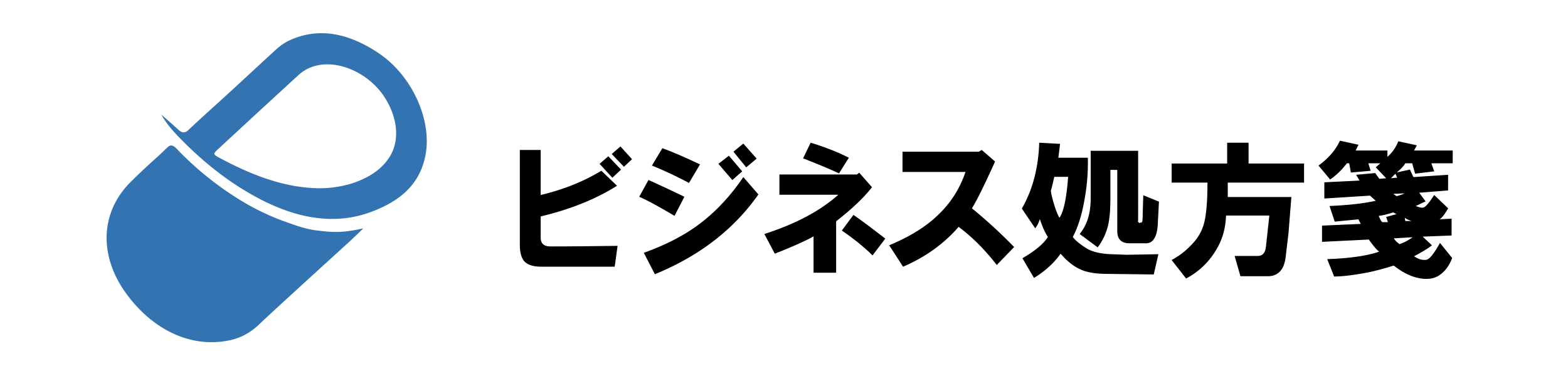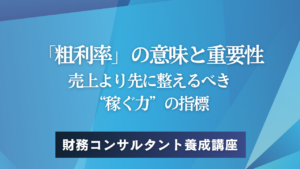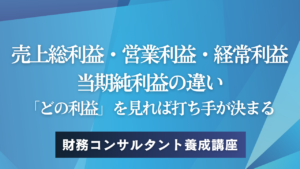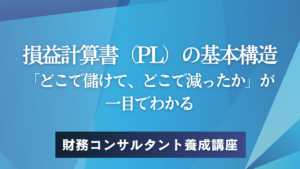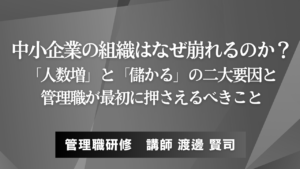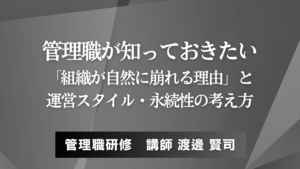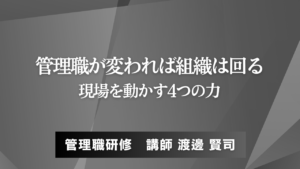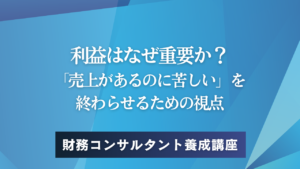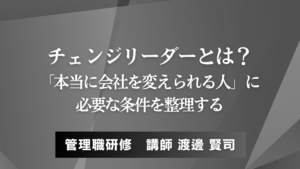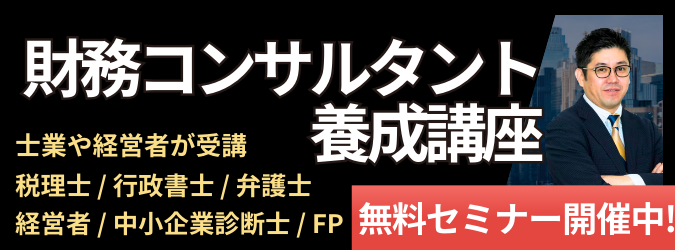経営計画の基本構成と成功事例:中小企業が知るべき実践ポイント

金親 正和
中小企業診断士
中小企業診断士 / 宅地建物取引士 / 不動産コンサルティングマスター
賃貸不動産経営管理士 / 管理業務主任者 / 防災士
大学卒業後、総合不動産会社にて不動産の企画・開発、賃貸物件のリーシング・管理(5,000室)、売却(半年間で46物件)と入口から出口までの業務に従事。
現在は、「補助金を通じて、中小企業経営者の皆様を支えたい」という思いから、各種補助金の申請支援に注力している。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
第1章:そもそも経営計画とは何か?
経営計画の定義と目的
経営計画とは、企業が中長期的な目標を達成するために、「どこに向かい、どのような手段で、どのようなステップを踏んでいくのか」を具体的に示す設計図のようなものです。
単に数字を並べるだけの資料ではなく、企業の未来を言語化・構造化する極めて重要な経営ツールです。
目的は大きく3つに整理できます。
第一に、「自社の方向性を明確にし、社員全体に浸透させること」
第二に、「金融機関や投資家、行政などの外部ステークホルダーに対して、自社の信頼性や成長性を示すこと」
第三に、「自社の成長スピードを加速させるために、経営判断を迅速・的確に下すための基盤とすること」
多くの中小企業では、代表者の頭の中に戦略や構想があるものの、それが明文化・共有されていないケースが少なくありません。
だからこそ、経営計画を“見える化”し、組織全体で共有することが、持続可能な成長の第一歩となるのです。
「経営戦略」「事業計画」「資金計画」との違い
経営計画と混同されやすい言葉として、「経営戦略」「事業計画」「資金計画」があります。これらは経営計画の“構成要素”と捉えると整理がしやすくなります。
| 用語 | 概要 |
| 経営戦略 | 市場・顧客・競合を踏まえた企業全体の方針・方向性を定めるもの |
| 事業計画 | 経営戦略に基づき、特定事業の展開方針・商品開発・販売方法などを具体化したもの |
| 資金計画 | 上記を実行するために必要な資金の流れ・調達手段・投資配分を定量的に示したもの |
つまり、経営計画とは「戦略(方向性)」と「戦術(手段)」、そして「数字(実行可能性)」を統合した包括的な実行計画といえます。
経営計画が求められる主な場面
経営計画は、単なる経営者のための【管理ツール】ではありません。
むしろ、外部に対する説明や信用力の源泉として、以下のような場面で強く求められます。
1. 金融機関からの融資申請時
金融機関は、融資先の安全性や収益性、将来性を重視します。
「いま資金が必要な理由」と「その資金が将来どのように利益に結びつくか」を説得力あるロジックで示すためには、経営計画が不可欠です。
とくに政策金融機関では、審査の際に明文化された経営計画書の提出が事実上の必須要件となっています。
2. 各種補助金・助成金の申請時
たとえば、ものづくり補助金、大規模成長投資補助金など、近年の補助金制度では「将来の成長性」「賃上げへの意欲」「省力化・生産性向上」などが求められており、単なる事業アイデアでは不十分です。
経営全体を見渡した事業戦略の一部としての計画が求められるため、経営計画の整備を推奨します。
3. 社内の方向性共有・人材マネジメント
とくに従業員数が増加してくる成長企業においては、経営者の思いを言語化し、社員と共有することが組織力を高めるうえで重要です。
目標や優先順位が曖昧な企業では、人材流出や業績停滞を招くリスクが高まります。
経営計画は【人を動かすための地図】でもあるという視点が重要です。
第2章:経営計画を作るべき3つの理由
経営計画は、単なる未来の数字予想ではなく、企業の意思を形にし、社内外のステークホルダーを巻き込み、持続的成長へと導くための「共通言語」です。
この章では、なぜ経営計画が重要なのか、その理由を3つに分けて解説します。
1. 社内の方向性を明確にするため
中小企業では、経営者と社員の距離が近い一方で、「会社がどこに向かおうとしているのか」が明文化されていないケースが多く見受けられます。
その結果、社員が日々の業務に疑問を持ったり、改善提案をしづらい空気が生まれたりします。
経営計画を作ることは、経営者が頭の中に持つビジョンや戦略を言語化し、「会社として進むべき方向性」を社内で共有するプロセスでもあります。
社員は、自分の仕事が経営目標とどう結びついているのかを理解することで、当事者意識を持ちやすくなり、エンゲージメントが高まります。
特に、複数部門が存在する企業においては、部門間の優先順位の認識がズレることが業務の非効率や摩擦を生みます。
経営計画を軸にした社内共有は、「全体最適で考える文化」の土台を築くうえで不可欠です。
2. 金融機関や投資家からの信頼を得るため
融資や出資といった外部資金を受ける際、金融機関や投資家が最も重視するのは「その企業がどれだけ真剣に未来を見据え、経営の舵取りをしているか」です。
つまり、財務諸表や担保といった過去や現在の数字だけでなく、将来のビジョンや再現可能な成長戦略の有無が評価ポイントとなるのです。
その際に必要不可欠なのが、体系的にまとめられた経営計画です。
収益構造や市場分析、投資戦略、人材育成、キャッシュフローの見通しが論理的に整理されていれば、金融機関は「この会社は計画性がある」「資金を貸し付けても回収できる」と判断しやすくなります。
近年、政策金融公庫や地銀、信用金庫などでも、融資判断における「計画書の質」が明確に問われるようになっています。計画の有無が、資金調達の成否を分ける現実があるのです。
3. 計画的に利益とキャッシュを生み出すため
企業が持続的に成長するには、感覚やコツ、経験だけに頼るのではなく、「数字に基づいた経営判断」が不可欠です。
経営計画は、売上・利益・資金繰りといった財務指標を体系的に整理し、いつ・何に投資し、どのタイミングで回収するかを見通すための「数字の地図」となります。
たとえば、新商品を出すにあたって「いつ開発費を投下し、どのくらいで回収するか」「初年度は赤字でも2年目以降に黒字化する見込みがあるのか」といった判断は、感覚だけで下すべきではありません。
事業ごとの採算性、利益率、固定費の構造などを明確にしたうえで、中長期的な視点から意思決定を行う必要があります。
また、キャッシュフロー計画を組み込むことで、「黒字倒産」のリスクも回避できます。帳簿上は利益が出ていても、実際の資金が不足すれば事業は続けられません。
経営計画には、利益と現金を<両輪>で設計する意識が求められます。
第3章:経営計画の基本構成【ひな形つき】
経営計画を作成する上で重要なのは、内容を「誰のために、どのように使うか」を明確にすることです。
例えば金融機関との対話材料として使うのか、社内の方向性共有ツールとして使うのかで、強調すべき部分が異なります。
しかし、あらゆる目的に対応できる汎用性の高い構成というものは存在します。
ここでは中小企業が自社で策定・活用しやすい経営計画の構成要素を紹介し、ひな形としても活用できるよう整理します。
1. 企業理念・ビジョン
経営計画の冒頭には、会社の「存在意義」や「目指す姿」を明記します。これは数値計画に入る前に、会社が何のために存在し、どんな未来を描いているのかを明文化するパートです。
■企業理念(例:地域社会への貢献、顧客満足の追求)
■ビジョン(例:5年後に国内トップクラスの〇〇企業になる)
ここが曖昧だと、全体の計画に一貫性がなくなり、社内外の信頼性を損なうリスクがあります。
2. 外部環境分析(市場・競合)
PEST分析や3C分析を用いて、自社を取り巻く外部環境を客観的に把握します。
■市場動向(人口減少/業界の成長率/顧客ニーズの変化)
■競合状況(競争の激化/価格競争の状況/新規参入)
■顧客・チャネル(主要顧客層、販売先の変化、DXの影響)
ここでは可能な限り数値を使い、出典も記載することで説得力が増します(例:総務省、経済産業省、中小企業白書など)。
3. 内部環境分析(強み・弱み)
SWOT分析やバリューチェーン分析を活用し、自社の資源やノウハウを構造的に把握します。
■強み:技術力、ニッチ市場での地位、熟練人材、独自の仕組み
■弱み:販路依存、属人的な業務体制、ITリテラシー不足
■機会:海外市場の拡大、インバウンドの拡大
■脅威:業界内の競争激化、急速な技術革新による製品の陳腐化
クロスSWOT分析は、SWOT分析を基に戦略を具体化するための手法です。
それぞれの要素を掛け合わせ、強みを活かし、弱みを克服しながら、機会を最大限に利用し、脅威に対処するための具体的な戦略を導き出します。
この分析によって、後述する「経営課題」や「戦略」の土台が形成されます。
4. 経営課題の整理
外部と内部のギャップから導き出されるのが「経営課題」です。たとえば、強みの一つである商品力に対して販路が弱ければ「販路強化」が課題となります。
課題は抽象的ではなく、実行可能なレベルに分解します。
■販売面:既存取引先依存 → 新規営業体制の構築
■生産面:歩留まりの悪さ → 製造ラインの改善とDX導入
■財務面:資金繰りの不安定さ → 運転資金管理の見直し
5. 中期の経営戦略(3〜5年)
中期戦略は、「どの市場で・誰に・何を・どう売るか」というマーケティング4Pと、事業ポートフォリオの見直しを軸に構成します。
■新商品/新サービスの開発計画
■地域拡大(県外進出/海外展開)
■アライアンスやM&Aによる成長戦略
また、人的資本の投資(育成・採用)や、生産性向上のための設備投資もこのパートで扱います。
6. 年度別アクションプラン
中期戦略を年次に落とし込むことで、「今年やるべきこと」が明確になります。これが社内マネジメントやKPIの基準となります。
(例)
| 年度 | 主要アクション | 責任者 | 成果指標(KPI) |
| 2026年度 | ECサイト立上げ | 営業部長 | 月商300万円 |
| 2027年度 | 新工場稼働準備 | 製造部長 | 生産能力150%向上 |
7. 財務計画(売上・利益・資金繰り)
計画の最終章は、定量目標を示す「数字の裏付け」です。PL(損益計算書)、BS(貸借対照表)、CF(キャッシュフロー計算書)をバランスよく盛り込みます。
■売上:主要製品・チャネル別の予測を記載
■利益:原価・販管費の見直しを反映
■資金繰り:投資回収期間、運転資金の確保
また、補助金・融資・出資など外部資金を活用する計画がある場合は、その根拠と財源内訳を詳細に記載することが求められます。
第4章:経営計画作成の手順とポイント
経営計画は、単なる【資料作成】ではありません。
「現場に根ざし、経営判断を導くための羅針盤」であり、作って終わりではなく、経営に活かして実践し、また作り直していくことこそ価値が生まれます。
ここでは、計画策定を成功に導くための4つのステップと、それぞれの実務的ポイントを解説します。
ステップ1:現状分析と目標設定
経営計画の出発点は「現状を正しく知ること」です。ここで曖昧な認識のまま進めてしまうと、机上の空論になってしまいます。
【現状分析のポイント】
■財務データ分析:売上構成比、利益率、固定費の内訳、キャッシュフローなど
■業務プロセスの棚卸:受注~納品、購買~在庫、業務の属人化やムダの把握
■ヒアリング・アンケート:現場社員や管理職へのインタビューを通じた定性的な実態把握
現状分析が終わったら、中期(3~5年)の目標を設定します。このとき、数字だけでなく「どういう状態を目指すか(質的目標)」も含めて定義することが重要です。
【目標設定の留意点】
「売上10億円」「経常利益率10%」のような財務指標だけでなく、「社員が誇りを持って働ける組織づくり」「顧客満足度の向上」など非財務目標も組み込む
ステップ2:数字に落とし込む(PL、BS、CF)
経営計画は数値化してはじめて「判断基準」として機能します。単なる願望や理想で終わらせないために、計画の各要素を財務3表(PL/BS/CF)に落とし込みます。
【PL(損益計算書)】
■売上高の予測(既存・新規・キャンペーン等の内訳)
■原価率、販管費の見直し
■利益率の改善目標(粗利率・営業利益率)
【BS(貸借対照表)】
■設備投資に伴う資産の増減
■借入金の増減と返済計画
■資本増強・自己資本比率の改善目標
【CF(キャッシュフロー)】
■運転資金の必要額と月次キャッシュ残高
■投資CF(設備投資・ソフトウェア導入など)
■財務CF(融資・補助金・増資の資金流入)
これらを3年または5年分作成することで、銀行や投資家にとっても信頼性のある資料となり、社内でも戦略実行の基準になります。
ステップ3:関係者とのすり合わせと見直し
計画は「経営者だけのもの」ではなく、実行するのは現場の部門長や社員です。そのため、早い段階で関係者を巻き込み、方向性や実行可能性について合意形成を図ることが欠かせません。
【すり合わせの実務的手順】
■部門長へ目標の意図を説明・意識合わせ
■実行プランとKPIについてディスカッション
■フィードバックを受けたうえで再度計画を調整
これにより、現場の温度感に合った「実行可能な計画」が形成され、社員の納得感も高まります。
ステップ4:モニタリング体制の構築
計画は「作って満足」で終わっては意味がありません。定期的な進捗確認と修正があって初めて、実効性ある経営計画となります。よって、PDCAを回すことが会社の成長につながります。※P:Plan、D:Do、C:check、A:Action
【PDCAを回す仕組み】
■月次の予実管理(目標数値との乖離分析)
■進捗報告会の設定(月1回など定例化)
■中間レビュー(半年ごとに方針や戦術の見直し)
さらに、外部の中小企業診断士や支援機関と連携することで、客観的な視点や最新の業界情報を取り入れながら、より実践的な運用が可能になります。
第5章:実際の成功事例に学ぶ!経営計画で企業が変わったケース
経営計画の本当の価値は「未来を描く力」だけでなく、「実行する力」を引き出すことにあります。この章では、経営計画によって大きな変化を遂げた3つの成功事例を紹介します。どの企業にも共通するのは、「数字と現場をつなぐ設計図」が、経営の分岐点で重要な役割を果たしたことです。
事例1:経営計画に基づいて資金調達を成功させたA社(製造業・年商4億円)
A社は金属加工を行う老舗の町工場で、老朽化した工作機械の更新に向けて数千万円規模の資金調達を検討していました。しかし、当初は金融機関との対話が進まず、設備投資の実現が見通せない状況でした。
そこで社長は、中小企業診断士に相談し、アドバイスを受けながら経営計画の立案を行いました。
まずは現状分析に基づき、製品別の利益率を可視化し、儲かる仕事・儲からない仕事を仕分けました。
その結果、「ある特定の加工工程で利益率が著しく高い」という強みを発見し、そこに経営資源を集中する戦略を策定しました。
新機械の導入によって生産性が何%向上し、結果として売上・利益がどう改善するかを定量的に示しました。
完成した経営計画は、金融機関にとっても納得性が高く、結果として希望通りの融資が実行されました。経営者は「経営計画で話が通じるようになった」と語り、社内にも前向きな空気が生まれました。
事例2:経営計画を軸に新規事業を立ち上げたB社(サービス業・年商1.2億円)
B社は個人向けの教育サービスを提供する企業でしたが、既存事業の伸び悩みにより将来の成長性に不安を抱えていました。社長は漠然と「法人向け研修もやりたい」と考えていたものの、実行には至っていませんでした。
そこで社長は、商工会議所の経営相談を通じて、中小企業診断士からのアドバイスをもらいました。相談を通じて明らかになったのは、「個人向けのノウハウを法人にも展開できる余地が大きい」ことと、「既存顧客との関係性を活かせるネットワークがある」という点。それらを基に、法人研修事業の立ち上げに向けた5年計画を策定しました。
具体的には、初年度は試験的に3社へ無償提供し、2年目以降に有償展開する収益モデルとしました。この戦略は、社内の営業担当にも明確なアクションを示すもので、モチベーションが上がりました。現在では法人事業の売上が全体の30%を超え、B社の成長ドライバーとなっています。
事例3:経営幹部の意識が統一され、業績改善につながったC社(卸売業・年商8億円)
C社は地域密着型の専門商社で、数名の幹部社員が担当する分野をそれぞれ任されていましたが、意思決定が属人化しており、方向性のズレがしばしば業績の足かせとなっていました。
困っていた社長は、中小企業診断士へ相談し、経営計画作成ワークショップを幹部社員とともに行いました。
経営理念から始まり、各部門のKPI、役割分担、財務目標をチームで練り上げる過程を中小企業診断士が伴走しました。特に、SWOT分析・3C分析・バリューチェーン分析を使って「社内でやるべきこと」と「外部に委託すべきこと」を整理したことで、業務効率が大幅に向上しました。
この結果、毎月の幹部会で予実のレビューと改善策が議論されるようになり、単月黒字化を12カ月継続。従業員満足度も向上し、離職率が3年連続で減少するなど、組織の一体感が生まれました。
成功企業に共通する3つの視点
これらの事例から導き出される共通項は以下の3点です
■「定量」と「定性」の両面で現状を把握している
■具体的な行動計画があることで、社内の行動が変わる
■中小企業診断士などの外部の視点を取り入れることで、盲点を克服している
経営計画は、経営者が「自分の考えを整理する」ための手段であると同時に、社内外に「納得してもらう」ための強力なコミュニケーションツールです。
第6章:経営計画を「作って終わり」にしないために
多くの企業が経営計画を作成する際に陥りがちな落とし穴は、「立派な計画を作ったものの、その後の活用がされない」という点です。経営計画は【作ること】がゴールではありません。むしろ、【動かすこと】【継続すること】にこそ意味があります。
この章では、経営計画を日々の経営活動にどう根付かせていくか、その実践的なポイントを解説します。
1. PDCAを回すための仕組みづくり
経営計画は「設計図」です。実際に建築物(=会社の未来)を形にするためには、計画(Plan)に基づいた行動(Do)、進捗管理(Check)、改善(Act)を絶えず繰り返す仕組みが必要です。
【実践ポイント】
P(Plan):3年・5年の中期経営計画を立案し、1年ごとに行動計画へブレイクダウン。
D(Do):部門ごとに具体的な実行担当者とスケジュールを設定。
C(Check):毎月の幹部会議でKPI・財務指標の予実管理を行う。
A(Act):未達の原因分析と再設定を柔軟に実施。
多くの中小企業では、CとAが疎かになりがちです。たとえ予実がズレても、それを正直に認識し、建設的な改善策を話し合える文化こそ、持続的な成長の土台です。
2. 社内での定期的な共有・レビュー
せっかく策定した経営計画も、経営層だけが把握し、現場に共有されていなければ意味がありません。むしろ、現場が納得して実行しなければ成果は上がりません。
【社内共有の工夫】
■全社員ミーティングでビジョン・戦略を共有
→月次や四半期ごとに経営状況の説明会を行い、社員に「自分ごと」として捉えてもらう。
■部門別KPIの“見える化”
→現場の行動がどう経営成果に結びついているかを「数値+言葉」で伝える。
■現場の声を経営会議に反映
→現場の課題や改善案を吸い上げる仕組みを整備。
これにより、「経営は社長だけのものではない」という一体感が生まれ、社員のエンゲージメントが高まります。
3. 支援機関・コンサルタントとの連携
PDCAを回す上で「外部の視点」も非常に有効です。第三者の冷静な目線で進捗や戦略の妥当性を検証し、定期的に振り返りを行うことは、経営者自身の思考をアップデートするきっかけになります。
【中小企業を活用すべき支援例】
■中小企業診断士との顧問契約
→月1回の振り返り、KPIの評価、財務管理のアドバイスなど。
■よろず支援拠点・ミラサポ等の支援制度
→補助金申請時だけでなく、計画の実行段階においても無料で相談可。
■伴走型支援の活用
→経営課題を継続的にサポートする制度も各自治体・機関で充実しています。
特に当社(株式会社3Rマネジメント)では、「計画策定支援」だけでなく「実行支援」「進捗レビュー」を含めた継続的な伴走支援を強みとしています。
最初から完璧な計画を作る必要はありません。【動かしてから磨く】ことが成功への近道です。
まとめ:経営計画を動かすのは「人と仕組み」
経営計画を成功に導く最大の要素は、「実行する人」と「運用する仕組み」です。逆に言えば、どれだけ立派な経営計画があっても、それを実行しない、運用しないのであれば意味はありません。
■社内での共有体制があるか?
■月次で振り返る仕組みがあるか?
■外部の視点を取り入れて改善しているか?
これらが回り始めることで、経営計画は「成果を生むツール」へと進化します。