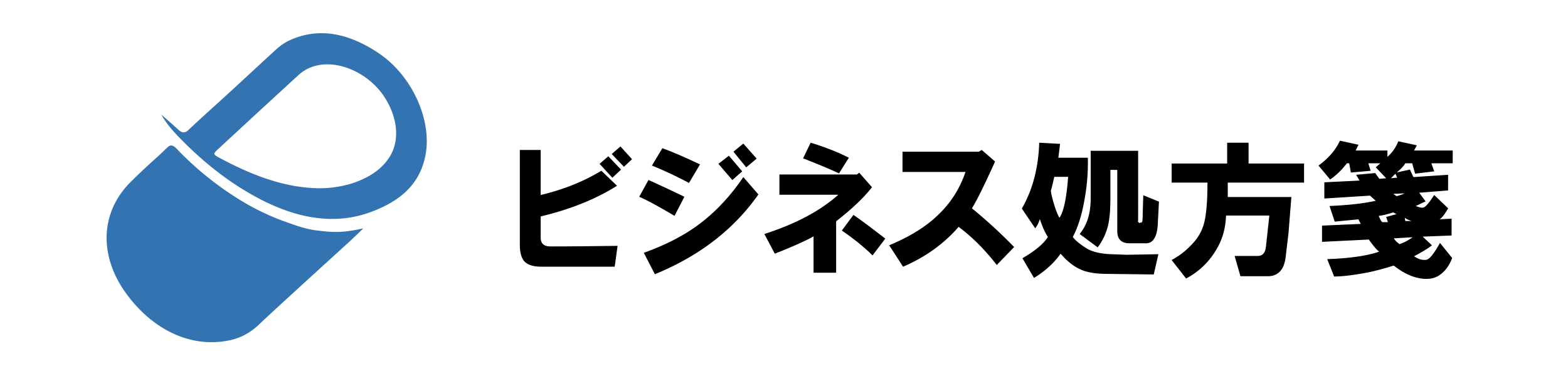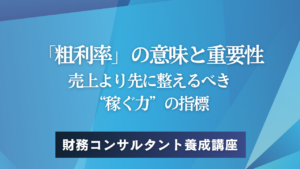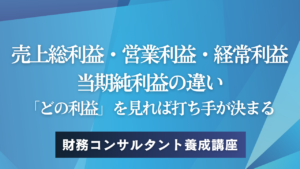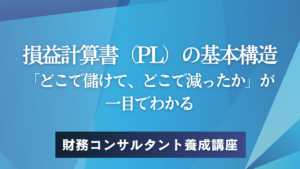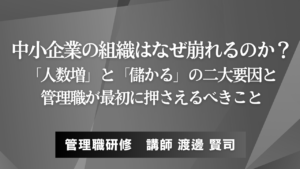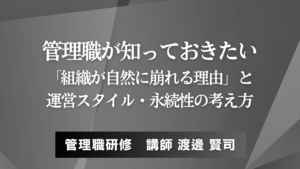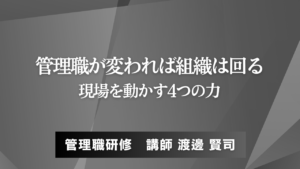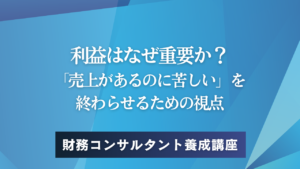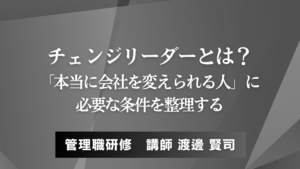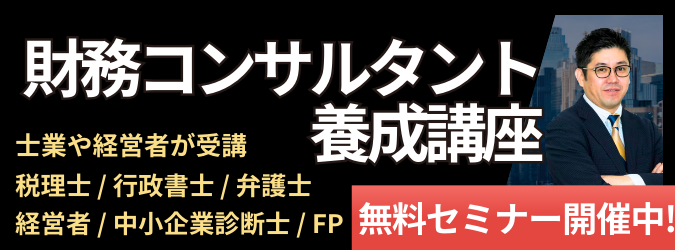補助金申請代行の法改正ガイド:2026年施行で何が変わる?

猪俣 友樹
中小企業診断士/
E資格
中小企業診断士/JDLA Deep Learning for Engineer(E資格)
ノンバンクでAI、データ分析を活用したマーケティング、リスク管理業務に従事。
データを駆使した課題解決や与信モデルの構築・運用を経験。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/
行政書士法改正の背景
行政書士法の改正は、行政手続きのデジタル化が進展し、電子申請やマイナポータル、GビズIDなどを利用したオンライン手続きが社会で一般化したことを主な背景としています。
総務省の通知では、「デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化している」とされています。この状況を受けて、国民の利便性向上や業務範囲・責任の明確化を図るため、2026年1月に行政書士法の一部改正が施行される見込みです。
※参考:行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)
2026年1月施行の改正内容
2026年1月1日の改正行政書士法の主なポイントは以下の通りです。
- 独占業務の範囲の明確化
報酬を得て官公署に提出する書類(補助金申請書を含む)を作成する業務や、電子申請の代理操作は行政書士の独占業務であることが明確化される見込みです。
- 電子申請システムでの代理提出等の法的位置付けの明確化
行政書士資格を持たない者によるGビズIDやマイナポータルを利用した代理申請、いわゆる「丸投げサービス」については、引き続き規制対象とされる予定です。
- 相談・助言・添削業務は引き続き他士業等でも提供可能
申請内容の助言・記載例の提供・添削、事業計画策定時のコンサルティング、電子申請手順の指導等は相談業務の範囲とし、行政書士以外の専門家も提供可能。 - 違反行為への罰則の明確化
行政書士法違反となる有償での作成代行・代理申請などには行政罰・刑事罰が科される可能性があることが再確認されています。
中小企業診断士等の支援業務と行政書士独占業務の区分
行政書士法は「書類の作成」と「相談業務」を明確に区分しており、支援内容によって取り扱いが異なります。
行政書士の独占業務として該当するのは、補助金申請書の作成代行、事業再構築計画書の作成代行、官公署提出用書類の代理作成、GビズIDを使用した電子申請システムでの代理提出、申請者に代わっての書類提出手続きなどです。これらの業務については、行政書士資格を持たない者が行うことは今後制限される見込みです。
一方で、相談業務については資格を問わず提供可能な範囲が残ると考えられます。事業計画策定に関する助言・コンサルティング、申請書内容の添削・校正、記載例やテンプレートの提供、電子申請システム操作方法の説明・指導、計画策定の手順整理・アドバイス、申請戦略の立案支援、必要書類の整理・準備指導などが該当します。これらの相談業務については、中小企業診断士や経営コンサルタント等が引き続き提供することが可能です。
補助金申請支援の具体的なケース解説
実際の支援現場では、どのような業務が行政書士独占業務に該当する可能性があり、どのような支援が相談業務として認められる傾向にあるのか、具体的なケースで解説します。
① 代行作成・代理提出のケース
申請者から依頼を受け、事業計画書や申請書を専門家が作成し、GビズIDで代理提出する行為は、行政書士の独占業務に該当すると考えられます。行政書士資格を持たない者がこのような包括的な代行サービスを行えば、行政書士法に違反するリスクが高いとされています。
② 添削・アドバイスのケース
申請者が自ら作成したドラフトに対して、構成や表現の改善提案を行うのは合法的な相談業務であり、他士業も提供可能です。専門家は助言者(アドバイザー)の立場にとどまります。
③ 電子申請システムの操作指導
GビズIDの取得方法説明や操作手順解説は支援可能。ただし実際のログインや提出操作は申請者本人が行う必要があります。
④ テンプレートや記載例の提供
汎用的なひな形・サンプルの提供は相談業務として認められますが、特定申請者向けにカスタマイズした作成は独占業務に近づくため注意が必要です。
信頼できる専門家の選び方とチェックポイント
法改正後も安心して補助金申請支援を受けるため、専門家選びの際は慎重な判断が求められます。
契約内容や広告表現において、「申請書の完全代行」「書類作成を丸投げOK」「代理提出サービス」「申請手続きを全て代行」「GビズIDでの提出まで一括対応」といった表現を使用している専門家については、法改正後の業務範囲に適していない可能性があります。
一方で、「申請書作成の助言・支援」「事業計画策定のコンサルティング」「申請戦略の立案支援」「書類添削・校正サービス」「電子申請操作の指導」といった表現を用いている専門家は、相談業務の範囲内でのサービス提供を意識していると考えられます。
専門家の資格・立場については、正確な資格(行政書士、中小企業診断士、税理士等)、認定支援機関としての登録状況、補助金申請支援の実績と専門分野、提供する支援内容の具体的範囲、責任の所在と契約条件を確認することが重要です。
申請プロセスにおいて、申請者本人が必ず行うべき事項として、本人確認手続きの完了、GビズIDの取得・管理、最終的な申請書類の内容確認、電子申請システムでの提出操作等があります。
申請者と専門家は、それぞれの役割と責任を明確に分担し、リスクを避けながら効果的な申請準備を進める必要があります。専門家はアドバイザーとしての立場を保ち、申請者は最終的な決定権および責任があることを理解することが重要です。
まとめ:安心・確実な補助金申請のために
2026年1月の行政書士法改正は、補助金申請代行業務の適正化を図る重要な制度変更です。申請者にとっては、行政書士以外の専門家からも、相談業務として支援を受けることは可能と考えられます。事業計画の策定支援、申請戦略の立案、書類の添削・改善提案など、価値の高いサービスを受けることができる見込みです。
法改正により、申請者自身の書類作成能力や申請手続きに対する理解がより重要になります。専門家の支援を受けながらも、最終的な申請責任を適切に果たせるよう、必要な知識を身につける必要があります。
法改正後の補助金申請環境では、申請者と専門家がより適切な役割分担のもとで協力し、透明性の高い申請プロセスを構築することが求められます。
補助金は中小企業の成長と発展を支える重要な制度です。法改正を機に、より健全で持続可能な支援体制のもと、事業者の皆様が安心して制度を活用できる環境が整備されることが期待されます。適切な支援を受けながら、確実で効果的な補助金申請を実現していきましょう。
\認定支援機関!補助金のプロの中小企業診断士がサポート/